新しい職場に飛び込んだあと、「前の会社のほうが良かったかも…」「こんなはずじゃなかった」と感じていませんか?
実は、20〜30代で転職を経験した人の多くが入社後に何らかの後悔を抱えており、その割合は調査によれば6割以上にも上ります。
さらに別のアンケートでは、過去の転職を「失敗だった…」と振り返る人が全体の約86%にも達しました。転職後にギャップを感じて「やっぱり辞めなければよかった…」と思うのは決して珍しいことではないのです。
では、なぜそのような後悔が生まれるのでしょうか?
本記事では、転職者によくある後悔の理由を幅広く紹介し、後悔しないための具体的な対策を多角的に解説。
転職を成功させたい方、過去の転職で苦い思いをした方はぜひ参考にしてみてください。
転職で後悔する主な理由
転職後のミスマッチによる後悔はなぜ起こるのでしょうか。
人それぞれ事情は異なりますが、多くの転職者に共通するパターンが存在します。あるアンケートでは、「収入」「仕事内容」「人間関係」「残業時間」「休日」といった項目で後悔を感じる人が特に多いことが分かりました。
ここでは、代表的な後悔の理由を具体的に見ていきましょう。

仕事内容のミスマッチによる後悔
「やりたかった仕事と違う」「聞いていた業務内容と実際がズレていた」といった仕事内容のミスマッチは、転職後の後悔理由としてよく挙げられます。
新しい職場で担当する業務が、自分の想定や希望とかけ離れているとモチベーションが下がり、「前の会社にいた方がよかったのでは…」と感じてしまいがちです。
実際、転職者の約4割が仕事内容に関して後悔を抱えているとの調査結果もあります。
例えば「企画職として採用されたのに実際は雑務ばかりだった」「最先端のプロジェクトに関われると思ったら、同じ作業の繰り返しだった」などのケースです。
また、自分のスキルや強みが十分に活かせない配置だと「この転職は失敗だった」と感じる要因になります。
仕事内容のミスマッチは短期離職の原因にもなりやすいため注意が必要です。
人間関係・社風の問題による後悔
人間関係や企業文化(社風)のギャップも、転職後によくある後悔ポイントです。
新しい職場の人間関係になじめず孤立したり、上司や同僚とうまくいかなかったりすると、精神的な負担から「転職しなければよかった」と感じてしまうことがあります。
アンケートでも約3割以上の人が人間関係に関する後悔を経験しており、「上司が思っていたタイプと違った」「チームの雰囲気が合わない」といった声が上がっています。
実際に、転職先で「上司が頼りない」「組織の風土が合わなかった」という不満が理由で後悔した人もいるようです。
前職では風通しの良いフラットな文化だったのに、転職先は年功序列が厳しく意見しづらい雰囲気だった場合、大きなカルチャーショックを受けるでしょう。
また、社内のコミュニケーションスタイルや働く上での価値観の違いもストレスになります。
職場の人間関係や社風になじめないギャップは、仕事上の悩みに直結しやすく、転職後の満足度を大きく下げる原因となります。
給与・福利厚生の悪化による後悔
転職によって年収や福利厚生が期待外れだったケースも、多くの転職者が後悔する理由の一つです。先の調査では、「収入」に関する後悔が最も多く、全体の46.0%にのぼりました。具体的には「転職してみたら給与額が事前の話より低かった」「ボーナスや各種手当の条件が聞いていた内容と違っていた」などの不満です。
基本給は上がったものの固定残業代込みの年収だったため実質的な手取りが期待より少なかった、前職ではあった住宅手当や退職金制度が転職先にはなく収入面で総合的にマイナスになった、というケース。
また、福利厚生についても「前の会社より休暇制度が整っていない」「リモート勤務やフレックス制度がなく不便」といった違いにショックを受けることがあります。
大企業からベンチャー企業へ転職した場合などは、医療保険や社内施設利用などの福利厚生が簡素化され、転職後に待遇低下を実感する人もいます。
収入や福利厚生の面でギャップがあると生活にも直結するため、転職後の後悔が強くなりやすい分野と言えるでしょう。
労働時間・働き方の悪化による後悔
労働時間や働き方(ワークライフバランス)の悪化も、転職後に「失敗した…」と感じる大きな要因です。
新しい職場で残業や休日出勤が増えてしまったり、有給休暇が取りづらかったりすると、私生活への影響も大きく、「前の職場のほうがマシだった」と後悔する人が少なくありません。
実際、「残業が増えた」「休日日数が減った」ことで転職を後悔したという人は調査で3割以上にのぼりました。
転職先から高い給与提示を受けて飛びついたものの、その分夜遅くまでの勤務や休日出勤が常態化しており、「こんなに働きづめになるなら辞めなければ良かった…」と感じるケースがあります。
逆に本当はワークライフバランスを重視した転職を目指していたのに、目先の条件(高年収など)に惹かれて入社を決めてしまい、結果的に長時間労働に苦しんで後悔する、という例もあります。
また勤務形態の変化(リモート可否やフレックス制の有無など)も生活リズムに影響します。
働き方の条件が事前の期待と食い違っていた場合、心身の負担から「失敗した」という思いが強まりやすいでしょう。
転職前にしっかり確認しておかなかった労働環境の違いが、後から大きな悔いとなって表面化するのです。
成長機会の欠如による後悔
「この会社では思うように成長できないかもしれない」——転職先でそう感じてしまうことも、後悔の一因となります。
せっかくスキルアップやキャリアアップを期待して転職したのに、いざ入社してみると成長につながる仕事や研修制度が不十分だったり、昇進の見通しが立たなかったりするケースです。
調査でも「成長・キャリアアップ」に関する後悔を抱える人は一部存在し、その多くが「成長につながる環境が整っていなかった」「キャリアアップできないポジションだった」と感じています。
例えば専門職で転職した場合、業務範囲が限定されてスキルの幅を広げられない、人手不足で毎日目先の業務に追われ新しいことが学べない、といった不満が生じることがあります。
また日本企業では、新卒入社者と中途入社者でキャリアパスが異なり、中途社員は出世コースから外れてしまう場合もあるようです。
こうした環境では「この会社では将来のキャリアアップが望めないのでは」と不安になり、転職したことを後悔することにつながります。
成長機会の欠如による後悔は発生率自体は他の要因に比べると低いものの、本人のキャリアビジョンとのミスマッチという点で深刻な失望につながりかねません。
後悔しないための事前準備
転職による後悔を防ぐためには、転職活動を始める前の段階での入念な準備が欠かせません。
自分自身の状況や希望を整理せずに「今の会社をとにかく辞めたい」と焦って転職してしまうと、かえって今より悪い状況に陥る可能性があります。
そうならないために、以下のポイントを事前に押さえておきましょう。
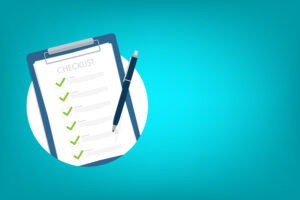
徹底した自己分析で「転職の軸」を明確にする
まずは自己分析を徹底し、自分の中の「転職の軸」を明確にすることが重要です。
転職の軸とは、「自分は何のために転職するのか」「仕事を通じて何を実現したいのか」という指針のこと。
これがあいまいなままだと、求人の条件や周囲の意見に流されて本来望まない選択をしてしまい、後々後悔するリスクが高まります。
そうならないように、以下の点を深掘りしてみましょう。
転職理由の洗い出し
現職で不満に感じていることや転職して実現したいことを書き出してみます。
「人間関係のストレスを減らしたい」「専門スキルを伸ばしたい」「年収を上げたい」など、自分が転職で得たいもの・避けたいものを整理します。
漠然と「何となく今の会社が合わないから…」では危険。
不満の本質や転職の動機を明確化することで、次の職場に求める条件も見えてきます。
例えば「上司との折り合いが悪い」が理由なら、次は社風や上司のマネジメント体制を重視する必要があるでしょう。
自己の強み・価値観の分析
自分の強みやスキル、働く上で重視したい価値観も再確認しましょう。
得意な業務や好きな仕事内容、反対に苦手な仕事や避けたい働き方をリストアップします。例えば「企画提案力が強み」「チームで協働するのが好き」などが分かれば、新しい職場を選ぶ際に自分が力を発揮できる環境か見極める指標になります。
また「ワークライフバランス重視」「成果主義より安定志向」など価値観の優先度も自覚しておくと、後述する条件の優先順位付けに役立ちます。
転職の目的と優先順位を設定する
自己分析を踏まえたら、次に転職の具体的な目的を言語化し、希望条件に優先順位を付ける作業を行いましょう。
転職によって何を最優先で実現したいのかを明らかにし、複数の希望がある場合はその優先度をはっきりさせておくことが大切。
すべての希望を完璧に満たす求人はなかなかないため、あらかじめ譲れる点・譲れない点を決めておく必要があります。
例えば「年収アップも大事だが、それ以上に残業の少ない職場で働きたい」というのであれば、「ワークライフバランス」を最優先条件に掲げます。
この場合、高年収でも激務の求人はミスマッチなので避ける、といった判断がしやすくなります。
逆に優先順位があいまいだと、目先の条件に釣られて本来重視すべきでない選択をしてしまいがち。
実際に「本当はプライベートの時間が確保できる職場を望んでいたのに、高年収に惹かれて転職を決めた結果、残業続きで後悔した」というケースもあります。
こうした後悔を避けるためにも、「勤務地」「給与」「仕事内容」「社風」など希望条件を書き出し、自分の中で何を優先するか順位付けしておきましょう。
優先順位が定まっていると、求人選択や面接の場でもぶれない軸を持って臨めます。
例えば第一優先が「キャリアアップ」なら、多少年収が下がっても成長機会の大きい企業を選ぶ、といった割り切りができます。目的意識と優先順位を明確に持つことは、後々「別の条件に気を取られて失敗した…」と悔やむのを防ぐ基本姿勢となります。
ャリア目標を明確にし、ライフプランと照らし合わせる
転職活動に入る前に、中長期的なキャリア目標を明確化しておくことも重要です。
5年後・10年後に自分がどうなっていたいか、そのために今回の転職でどんな経験や役割を得たいのかを考えてみましょう。
キャリアのゴールが見えていると、転職先で得るべきもの(経験・スキル・ポジション)がはっきりし、ミスマッチな選択を避けやすくなります。
例えば「将来はマネジメント層に就きたい」という目標があるなら、マネジメント経験を積める環境かという観点で企業を選ぶ必要がありますし、「専門スキルを極めて独立したい」ならその分野の実績を積める職場を選ぶべきでしょう。
目先の条件だけでなく将来の自分にとってプラスになる選択かどうかを考えることで、短絡的な判断による後悔を減らせます。
さらに、自身のライフプラン(人生設計)との整合性も確認しておきましょう。転職は仕事上の選択ですが、人生全体にも影響を与えます。
結婚や出産・育児、介護、居住地やマイホーム取得、将来の進学や留学など、今後予定しているライフイベントや描いている生活像に対して、転職後の働き方がフィットするかを検討します。
例えば「数年内に出産を考えている」のなら産休育休制度が整っている職場が望ましいですし、「地方へのUターンを考えている」なら将来転勤可能か在宅勤務可否も考慮したほうが良いかもしれません。
ライフプランと転職先の条件が大きく食い違うと、せっかく転職しても私生活との両立が難しくなり後悔する恐れがあります。
逆に言えば、仕事上の目標と私生活上の希望が両立できる道を選ぶことが、長期的な満足度につながります。
後悔しないための情報収集・確認ポイント
自分自身の準備が整ったら、次は転職先の実態をできる限り把握するための情報収集に力を入れましょう。
後悔の多くは「入社前に期待していたこと」と「実際に入社してわかった現実」とのギャップから生じます。
そのギャップを事前に埋めるために、様々な角度から入念に企業リサーチを行い、選考過程でも疑問点を確認することが大切。
ここでは、転職先を見極めるために有効な情報収集と確認のポイントを紹介します。

企業研究を徹底的に行う
まず基本として、志望企業の情報を徹底的に調べることが欠かせません。
応募先の公式ウェブサイトや採用ページに目を通すのはもちろんのこと、ニュースリリースや決算情報、業界内での評判などもチェックしましょう。
企業のビジョンや経営状況、今後の戦略を把握することで、自分の期待と合致しているかを判断できます。
特に重要なのは、求人票に書かれている情報だけで判断しないことです。求人票には好条件が並んでいても、それが社内の実態とイコールとは限りません。
「成長企業」と書かれていても具体的な成長率や事業内容を知らなければ実感は湧きませんし、「アットホームな職場」とあっても何をもってそう言っているのかは不明です。
できれば以下のような点も調べておくとよいでしょう。
●業績や業界ポジション
将来性や安定性を知るため、売上や利益の推移、主要事業の市場シェアなどを確認します。業績不振が続いているなら将来リストラの不安もありますし、急成長中なら業務量が多い可能性もあります。
●事業内容・プロダクト
実際に自分が関わるかもしれない製品やサービスについて理解しておきます。
その分野に興味が持てるか、社会的な意義があるかなども後悔しないためのポイントです。
●社風や理念
経営理念や社長メッセージなどから会社の価値観を読み取ります。
自分の働く上での価値観と大きくズレていないかチェックしましょう。
●人事制度
昇進・評価制度や教育研修制度もわかれば確認します。
社員の平均勤続年数や離職率などが公開されていれば、それも職場環境を知る手がかりになります。
社員の口コミサイトを活用する
公式情報だけでなく、社員や元社員の口コミ情報も重要な参考材料となります。
近年は「OpenWork(オープンワーク)」や「転職会議」「ミイダス」など、企業の内部情報を現社員・元社員が投稿する口コミサイトが普及しています。
こうしたサイトを活用すれば、社内の雰囲気や実態についてより生々しい声を知ることができます。
実際、就職・転職活動時に社員口コミサイトで企業情報を調べている人は約76.7%にも上るとの調査結果があり、多くの求職者が公式情報だけでなく口コミや評判もチェックしていることが分かります。
口コミサイトでは「残業は月◯時間程度」「上司との関係は○○」「年収は同業他社と比べて△△」など具体的な投稿が見られるため、自分の重視ポイントに関する実態を把握しやすいでしょう。
実際に社名で検索すると、「〇〇社 評判」「〇〇社 残業」などのキーワードで様々な声がヒットします。
ただし、口コミ情報を鵜呑みにしすぎない姿勢も大切。
投稿者の属性(部署や役職、在籍時期)によって感じ方は異なりますし、不満のある人の声が多めに投稿される傾向もあります。
そのため、極端に悪い評価があっても一つの意見として捉え、他の投稿や平均評価と照らし合わせて総合的に判断しましょう。
また、口コミで不安に感じた点こそ面接などで企業側に質問して確認してみることが重要です。
しかし実際には、口コミで不安を抱いた内容を入社前に企業へ確認しなかった人が85%もいるというデータもあります。
ネガティブ情報こそ曖昧なままにせず、次に述べる面接時の確認などで解消する姿勢が、後悔を防ぐ上で有効です。
面接で積極的に疑問点を質問する
選考の場(面接や内定後のオファー面談など)は、こちらから企業に質問できる貴重な機会です。
後悔しない転職のためには、この場をフルに活用して入社前の不安や疑問を解消しておきましょう。
特に、働いてみないと分からない職場の雰囲気や業務の進め方、人間関係の様子などは、事前に質問して聞き出すのが有効です。
質問するポイントの例: 具体的な業務内容の確認
面接では求人票以上に突っ込んだ業務内容を聞いておきます。
「入社後の具体的な担当業務は何か」「どのようなプロジェクトに携わる予定か」などを質問し、自分のイメージとズレがないか確認しましょう。
営業職なら「扱う商材や顧客ターゲット」「営業スタイル(新規開拓かルート営業か)」などを尋ねると安心。
また「自分と同じような経歴の中途入社の方はどんな業務を任されていますか?」といった質問で、同程度の人が活躍している具体像を探るのもいいでしょう。
質問するポイントの例: 残業や休日など働き方の確認
労働時間や休暇に関しても可能な範囲で質問しましょう。
「繁忙期の残業時間は平均どのくらいか」「有給休暇は取りやすい雰囲気か」「リモートワークの頻度」など、気になる点は具体的に聞くと現実的な回答が得られます。
直接「残業多いですか?」と聞きにくい場合は、「繁忙期には皆さんどのくらい働いているのでしょうか?」などと尋ねるとよいでしょう。
曖昧にせず働き方に関する条件面をすり合わせておくことが大切です。
質問するポイントの例: 給与・待遇の詳細確認
オファー段階では給与や各種手当の詳細、昇給・賞与の仕組みについてもしっかり確認します。
「提示された年収に残業代は含まれているか」「賞与やインセンティブの支給条件」「昇給のペースや評価反映の仕組み」など、入社後の金銭面でギャップが生じないよう具体的に質問しましょう。
求人票には大まかな年収しか書かれていないことも多いため、入社時点の給与額や内訳を明確にしておくことは後悔防止に不可欠です。
質問するポイントの例:職場環境・社風に関する質問
職場の雰囲気や人間関係に直結する質問もできればしておきたいところです。
「配属先のチームはどんなメンバー構成か」「上司や先輩社員とのコミュニケーションの取り方」「社内イベントや交流はあるか」などを聞けば、その会社の社風や人間関係のヒントが得られます。
直接「人間関係は良いですか?」と聞いても表面的な回答しか得られない可能性があるため、「○○さん(面接官)が所属する部署ではどんな雰囲気で仕事をされていますか?」などと具体的な状況を伺う質問にすると本音が引き出しやすくなります。
キャリアカウンセラーや転職エージェントを活用する
一人で転職活動を進めるのが不安な場合や、より客観的な情報・アドバイスが欲しい場合は、キャリアカウンセラーや転職エージェントといったプロのサポートを活用するのも有効です。
転職は人生の大事な決断ですから、第三者の視点を取り入れることで後悔のない選択に近づけます。
転職エージェントであれば、自己分析の支援から企業情報の提供、選考対策まで幅広くサポートしてくれます。
自分では気付かなかった強みを引き出してくれたり、希望に合った求人を紹介してくれたりするので、ミスマッチのリスクを減らすのに役立ちます。
特に、エージェント各社は独自に企業の内部事情を把握していることも多く、求人票には現れない職場のリアルな情報を教えてもらえる場合があります。
「この会社は残業が多めだが〇〇の制度でカバーしている」「社風は堅実で落ち着いた雰囲気」など、実際に過去の紹介実績から得た生の情報を持っていることもあるのです。こうした情報はネットの口コミには出ていないこともあるため、エージェント経由で知ることで事前の心構えや質問準備がしやすくなります。
また、キャリアカウンセラーとの面談を通じて自分の考えを整理することで、「本当に自分が求める条件は何か」「その企業で実現できそうか」を再確認できます。
複数の内定をもらった際の比較検討の相談などもプロに乗ってもらえるため、判断に迷ったときにも心強い味方となるでしょう。
エージェントの利用は基本的に無料で、在職中でもスケジュール調整を代行してくれるなどメリットが大きいです。
ただし、自分の軸がぶれないよう前述の自己分析は自分でもしっかり行い、エージェント任せにしすぎないことも大切。
総じて、第三者の客観的な意見や情報源を取り入れることで視野が広がり、思い込みや見落としによる後悔を防ぎやすくなります。
身近に転職経験者や相談できる先輩・同僚がいれば、体験談を聞くのも良いでしょう。
様々なリソースを活用して万全の準備で転職に臨めば、「しまった!」という失敗の確率はぐっと減らせるはずです。
まとめ:「転職をしてよかった」という声も多い
転職後によくある後悔のパターンと、そうした後悔を未然に防ぐためのポイントを紹介しました。転職は新たなチャンスである反面、不確定要素も多いため不安はつきものです。しかし、事前に自分自身と向き合って軸を定め、企業の実態を徹底的に調べ、疑問点を一つひとつ潰していくことで、理想と現実のギャップを最小限に抑えることができます。実際に転職経験者の多くが後悔を感じているからこそ、同じ轍を踏まないように準備と対策を怠らないことが大切です。
「転職しなければよかった…」と嘆く人がいる一方で、「転職して本当によかった!」「今の仕事に大満足している」という人ももちろん大勢います。
そういった成功者は、総じて綿密な情報収集と自己分析のもと、慎重かつ戦略的に転職活動を進めています。
最後にもう一度、後悔しないためのポイントを整理しておきましょう。
●自分の転職理由・目的を明確にする。
(焦って現職から逃げるのではなく、何を実現したいかを軸に据える)
●希望条件に優先順位を付ける。
(全てを求めず譲れない条件を決めておく)
●志望企業の情報収集を徹底する。
(公式情報+口コミや第三者の意見も参考に、実態を多面的に把握)
●面接等で不明点を確認する。
(遠慮せず質問し、入社前にモヤモヤを残さない)
●必要に応じてプロの力を借りる。
(転職エージェントや信頼できる人に相談し客観的な視点を取り入れる)
これらを実践すれば、転職によるミスマッチや後悔のリスクは大きく低減できるでしょう。せっかく掴んだ新天地でのチャンスですから、悔いのない選択をするためにできる準備はすべて行ってください。
慎重な準備と行動の末に手にした転職であれば、きっと「転職してよかった!」と思える日が訪れるはずです。
新しいキャリアが充実したものになるよう、心から応援しています。
株式会社アルファ・ネットコンサルティングは、特性やスキルセットを詳細に分析し、その強みや価値を明確に評価するTalent Match(タレントマッチ)というサービスを運営しております。
個々の特性やスキルを把握することで、それを活かせる職種や業界を特定、求人紹介やキャリアフェアなどの手段を活用し、適切な転職先を見つけるお手伝いをします。
今よりも活き活きと仕事ができる場所を探して転職活動をしている方、自社にピッタリの人材をお探しの企業様はサービスの概要をご確認ください。




