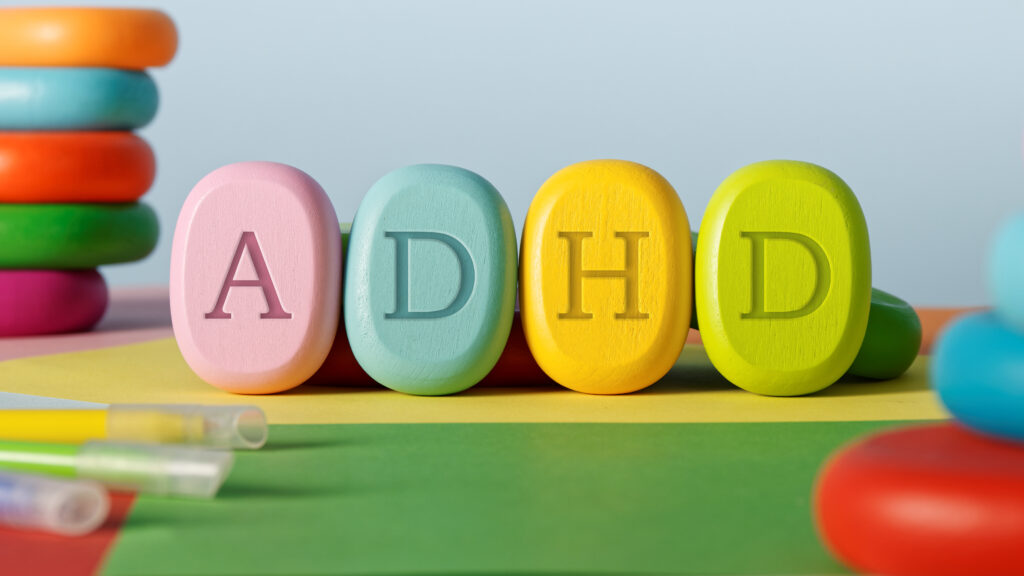ADHD(注意欠如・多動症)は子どもの発達障害として知られていますが、大人になっても症状が続くケースがあります。
大人のADHDでは「集中力が続かない」「スケジュール管理が苦手」「忘れ物が多い」といった特性が、仕事や人間関係に影響を与えることがあります。
しかし、適切な対策や環境の工夫によって、強みを活かしながら活躍することも可能です。本記事では、大人のADHDの特徴や仕事における影響、職場での対処法について解説。
自身の働き方や企業のサポート体制を考える際の参考にしてください。
大人のADHDとは?基本的な特徴と診断のポイント
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもだけでなく大人にも影響を及ぼす発達障害の一つです。
仕事や日常生活において困難を感じることがありますが、適切な理解と対策によって強みを活かすことも可能です。
ADHDとは何か?
ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)は、不注意、多動性、衝動性の3つの特性を持つ発達障害の一つです。
子どもの頃から症状が現れることが多いものの、大人になると行動パターンや環境によって現れ方が変化することがあります。
ADHDの特性は個人差があり、仕事や人間関係に影響を及ぼす場合もあれば、創造力や行動力を活かして活躍できる場合もあります。
自身の特性を理解し、適切な対応をとることが重要です。
大人のADHDと子どものADHDの違い
ADHDの特性は、年齢とともに変化します。
子どものADHDでは、授業中にじっとしていられない、宿題を忘れる、順番を待つのが苦手といった行動が目立ちます。
一方、大人のADHDでは、仕事のスケジュール管理が苦手、締め切りを守れない、会議で集中力が続かないなど、社会生活に影響を与える形で現れることが多くなります。
また、ストレスや対人関係のトラブルが増えることで、二次的に不安や抑うつなどの症状を伴うこともあります。
ADHDの主な特徴(不注意・多動・衝動性)
ADHDには不注意、多動性、衝動性の3つの主要な特徴があり、大人の場合もこれらの傾向が見られます。
●不注意(集中力の維持が難しい)
・仕事中に注意がそれやすく、ミスが多い
・会議や講義で話を聞いていても内容が頭に入らない
・物をなくしやすく、重要な書類を紛失することがある
・計画的に業務を進めるのが苦手
●多動性(じっとしていられない)
・会議中や長時間の作業で落ち着かず、体を動かしてしまう
・話しているうちに脱線しやすく、話題が次々に変わる
・じっと座っているのが苦痛で、移動を伴う仕事の方が向いている
●衝動性(考える前に行動してしまう)
・話の途中で相手の言葉を遮ってしまう
・衝動的に発言してしまい、後から後悔することがある
・計画を立てずに行動し、あとで修正することが多い
・感情のコントロールが難しく、イライラしやすい
ADHDの診断基準とセルフチェック方法
ADHDの診断は、医師による問診や行動観察をもとに行われます。
一般的な診断基準には、不注意・多動・衝動性の症状が6か月以上持続していることや、日常生活や仕事に支障をきたしていることが含まれます。
セルフチェックの方法としては、以下のような質問を自問してみるとよいでしょう。
・仕事や日常で頻繁にミスをすることがある
・締め切りを守るのが苦手で、ギリギリになってしまう
・話している途中で考えが飛びやすい
・衝動的に発言してしまい、人間関係に影響を与えることがある
・整理整頓が苦手で、机の上やカバンの中が散らかりがち
これらの傾向が強く、生活や仕事に支障をきたしている場合は、専門医に相談することを検討してみましょう。
適切な診断と対策によって、自分に合った働き方を見つけることが可能です。
大人のADHDが抱える主な課題
大人のADHDの特性は、仕事や人間関係、時間管理に影響を及ぼすことがあります。
自身の特性を理解し、適切な対策を講じることで、困難を軽減しながら能力を発揮することが可能です。

仕事でのミスが多い原因とは?
ADHDの特性として、不注意や集中力の維持が難しいことが挙げられます。
これにより、作業中にミスが発生しやすい傾向があります。
例えば、報告書の誤字脱字、重要なメールの見落とし、書類の紛失などが頻繁に起こることがあります。
また、業務の優先順位を決めるのが苦手なため、重要な仕事を後回しにしてしまい、締め切り直前に焦るといったケースも少なくありません。
対策として、タスク管理ツールを活用する、チェックリストを作成する、作業ごとにアラームを設定するなどの工夫を取り入れると、ミスを減らすのに効果的です。
人間関係でのトラブルの特徴
ADHDの衝動性や注意の散漫さは、対人関係にも影響を与えることがあります。
例えば、相手の話を最後まで聞かずに遮ってしまう、思ったことをすぐに口にしてしまうといった行動が、相手に誤解を与えてしまうことがあります。
また、会話中に別のことを考えてしまい、相手の話をしっかり聞いていないと思われることもあります。
さらに、感情のコントロールが難しく、イライラしやすい、衝動的に怒ってしまうといった場面も見られます。
これを防ぐためには、一拍置いてから発言する習慣をつける、相手の話を要約しながら聞くなどの方法を意識すると、円滑なコミュニケーションにつながります。
時間管理が苦手な理由と対策
ADHDの人は時間の感覚がつかみにくく、締め切りを守れない、スケジュール通りに行動できないといった課題を抱えることが多いです。
特に、「すぐに終わる」と思っていた作業に予想以上の時間がかかり、結果的に他の予定が遅れるという状況が頻発します。
また、優先順位の判断が難しいため、本来やるべき仕事よりも気になることを先に進めてしまうこともあります。
対策として、タスクを細かく分けて期限を設定する、ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)を活用する、事前に時間の見積もりを行うなどの方法が有効です。
ストレスや不安との付き合い方
ADHDの特性によって、仕事や人間関係での失敗が積み重なると、自己肯定感の低下やストレスの蓄積につながることがあります。
また、環境の変化や複数のタスクを同時に処理しようとすると、頭の中が整理できずに強い不安を感じることもあります。
これを軽減するためには、適度な運動を取り入れる、リラックスできる時間を確保する、考えを整理するためにメモを活用するなどの方法が効果的です。
また、周囲のサポートを受けながら、無理をしすぎない働き方を意識することも大切です。
大人のADHDが仕事で活躍するための工夫
ADHDの特性は、仕事の進め方に影響を与えることがありますが、適切な工夫をすることでパフォーマンスを向上させることができます。
自身の強みを活かし、職場環境を整えることで、より働きやすくなるでしょう。
仕事での集中力を高める方法
ADHDの人は、集中力が長時間続かないことが多いため、作業環境を工夫することが重要です。
例えば、ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)を活用する、作業ごとにタイマーを設定する、タスクを細かく分けるといった方法が効果的です。
また、周囲の音が気になる場合は、ノイズキャンセリングイヤホンを使う、静かな場所で作業するなど、環境を整えることも集中力向上につながります。
作業前に軽い運動や深呼吸を取り入れることで、脳をリフレッシュさせるのも有効です。集中できる時間を見極め、自分に合ったリズムを作ることがポイントとなります。
タスク管理をスムーズにするコツ
タスク管理が苦手な場合、「やるべきこと」が多すぎて混乱しやすいことが原因の一つです。これを防ぐには、タスクをリスト化し、優先順位をつけることが重要です。
例えば、「緊急度×重要度マトリクス」を活用し、今すぐ取り組むべきタスクと後回しにできるタスクを区別すると、効率的に仕事を進めやすくなります。
また、デジタルツール(Trello、Notion、Google Keepなど)を活用すると、タスクの可視化がしやすくなります。
さらに、「5分以内にできるタスクはすぐやる」「難しいタスクは細かく分解して1つずつこなす」といったルールを作ることで、スムーズにタスクを処理できるようになります。
職場の理解を得るためのコミュニケーション術
ADHDの特性を持つ人が職場で円滑に働くためには、周囲の理解を得ることが重要です。ただし、全てを正直に話すのではなく、業務に影響する部分だけを伝え、具体的なサポートをお願いすることが効果的です。
例えば、「スケジュール管理が苦手なので、リマインダーを設定するようにしています」といった形で対策を伝えることで、相手に安心感を与えることができます。
また、報連相を意識し、仕事の進捗や困りごとを早めに共有することで、周囲との連携をスムーズにすることも重要です。
適切なコミュニケーションを心がけることで、働きやすい環境を作ることができます。
大人のADHDのための仕事探しのポイント
ADHDの特性を活かせる仕事を選ぶことで、無理なく働きやすい環境を作ることができます。
向いている職種の見極め方や面接での工夫、転職活動の進め方など、仕事探しの際に押さえておきたいポイントを紹介します。

向いている職種と適性
ADHDの特性を持つ人材が活躍できる環境を整えることは、企業にとって重要な課題の一つです。
適性のある職種の選定や面接での対応、職場環境の工夫により、彼らの強みを活かし、企業全体の生産性向上につなげることが可能です。
そのため、営業職、マーケティング、デザイン、ライティング、エンジニアリング、企画職など、創造力や柔軟性が求められる仕事で強みを発揮しやすいと考えられます。
一方で、単純作業や正確性が求められる事務職や会計業務では、パフォーマンスを発揮しにくい場合も。
企業としては、適材適所を意識し、個々の能力が最大限活かせる業務に配置することが重要です。
面接での自己PRのコツ
ADHDの特性を持つ求職者との面接では、彼らの強みと、業務遂行上の課題への対策を確認することが重要です。
例えば、「新しいアイデアを生み出すことが得意」「スピード感を持って行動できる」といったポジティブな要素を持つ一方で、スケジュール管理や細かい調整が苦手であるケースがあるため、どのように自己管理しているかを具体的に尋ねることで、採用後のミスマッチを防ぐことができます。
採用担当者としては、「自己の課題をどのように克服しながら業務を遂行しているか」を確認し、適切な業務環境を整えられるかを見極めることが大切です。
職場選びでチェックすべきポイント
ADHDの特性を持つ社員が能力を最大限発揮するためには、明確な業務フローと適切なフィードバック体制を整えることが有効です。
例えば、タスク管理ツールの活用、報連相のルール設定、進捗確認の仕組みを導入することで、業務遂行のしやすさが向上します。
また、フレックスタイム制やリモートワークの選択肢を設けることで、集中しやすい環境を確保できる場合もあります。
企業としては、こうした仕組みを整え、特性に配慮した働き方を導入することで、組織全体の生産性向上につなげることができます。
転職活動の進め方と注意点
ADHDの特性を持つ人材の採用においては、適性を見極め、企業の求めるスキルや業務内容と適合するかを慎重に判断することが重要です。
転職市場では、彼らのスキルを活かせるポジションが広がっており、企業側がどのようなサポートを提供できるかによって、採用後の定着率やパフォーマンスに大きな差が生じる可能性があります。
採用プロセスにおいては、求職者自身がどのような働き方を希望しているのかを丁寧にヒアリングし、企業文化や業務プロセスとマッチする環境を提供できるかを見極めることが、長期的な雇用の成功につながるでしょう。
ADHDの人が使える支援制度と活用法
ADHDの特性を持つ人材が働きやすい環境を整えるために、企業側は適切な支援制度を活用することが求められます。
障害者雇用制度や合理的配慮、助成金制度などを理解し、適切に活用することで、雇用の安定と生産性向上につながります。
障害者雇用制度とは?
障害者雇用促進法に基づき、企業には一定割合の障害者を雇用する義務が課せられています。
ADHDも、診断を受けた場合には「精神障害者」として障害者雇用枠での就労が可能となります。
これにより、一般採用とは異なる枠組みでの就労が可能となり、職務内容の調整や配慮を受けやすい環境を確保できるメリットがあります。
企業側は、障害者雇用納付金制度や助成金を活用しながら、適切なサポートを提供することで、ADHDの特性を持つ社員の長期的な雇用を促進できます。
ADHD向けの就労支援サービス
ADHDの特性を持つ人材がスムーズに就職・転職できるよう、各種就労支援サービスが提供されています。
例えば、障害者職業センター、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などでは、職業適性診断や面接対策、職場適応訓練を行っています。
また、ジョブコーチ制度を活用すれば、職場での適応支援を専門家がサポートし、業務の進め方や環境調整をサポートすることも可能です。
企業としては、こうした支援サービスを活用しながら、ADHDの特性に応じた業務設計を行うことで、より円滑な職場環境を構築できます。
職場での合理的配慮の活用方法
ADHDの特性に配慮した職場環境を整備することは、生産性向上や離職防止につながる重要なポイントです。
合理的配慮とは、従業員が能力を最大限発揮できるよう、企業が適切な調整を行うことを指します。
具体的な配慮として、業務指示を具体的に伝える、タスク管理ツールを活用する、集中しやすい環境を整えるなどの工夫が挙げられます。
また、定期的な面談を実施し、業務の進め方に関するフィードバックを提供することで、ADHDの特性を持つ社員がより適応しやすい環境を構築することが可能です。
助成金やサポート制度の利用方法
企業がADHDの特性を持つ人材を雇用し、適切な支援を提供する際には、各種助成金や補助制度を活用することで、負担を軽減できます。
例えば、「特定求職者雇用開発助成金」や「障害者雇用安定助成金」などの制度を活用すれば、ADHDの人材を採用した際の給与補助や職場環境整備のための資金支援を受けることができるでしょう。
また、ジョブコーチ支援制度を利用すれば、専門家による職場適応の支援を受けながら、スムーズな職場定着を図ることも可能。
こうした制度を上手く活用することで、企業側の負担を抑えながら、ADHDの人材が長期的に活躍できる環境を整えることができます。
ADHDの特徴を強みに変える思考法
ADHDの特性は、仕事や日常生活において課題となることがありますが、視点を変えれば強みとして活かすことも可能です。
適切な環境と働き方を整えることで、個々の能力を最大限に引き出せるようになります。
「弱み」ではなく「個性」と捉える
ADHDの特性は、一般的に「集中力が続かない」「計画を立てるのが苦手」「衝動的な行動が多い」といった弱みとして捉えられることが多いですが、視点を変えることで創造力、行動力、柔軟な発想といった強みとして活かすことができます。
新しいアイデアを次々と生み出せることは、企画やクリエイティブな仕事での大きな武器になり、衝動的な行動は、瞬時の判断が求められる環境ではプラスに働くこともあります。
企業としては、ADHDの特性を「改善すべき弱点」としてではなく、「適材適所で活かせる個性」として捉えることで、人材の持つポテンシャルを最大限に活用できます。
個々に合った働き方を整える
ADHDの人材が能力を発揮するためには、画一的な働き方ではなく、個々に合った環境を整えることが重要です。
ルールや手順に縛られすぎる職場よりも、裁量権があり、自由な発想が求められる職種のほうが適している場合が多いです。
また、リモートワークやフレックスタイム制を導入することで、集中しやすい時間帯に業務を進めることが可能になります。
業側が柔軟な働き方を提供することで、ADHDの特性を持つ人材が長期的に活躍できる環境を構築できます。
自己理解を深めるためのヒントを与える
ADHDの特性を持つ人材が自身の強みを活かし、働きやすい環境を見つけるためには、まず自己理解を深めることが重要です。
自分の思考パターンや行動の傾向を把握することで、得意なことと苦手なことを明確にし、それに適した業務や環境を選択できるようになります。
自己理解を促す方法として、日記をつける、業務中の行動を記録する、フィードバックを積極的に受けるなどが挙げられます。
例えば、1日の仕事を振り返り、「スムーズに進められた業務」「つまずいた業務」「集中しやすかった環境」などをメモしておくと、自分の特性が見えてきます。
また、ストレングス・ファインダーや適性診断テストを活用し、自分の強みを数値化するのも効果的です。
これにより、客観的な視点で自分の特性を把握でき、適した業務スタイルの選択に役立ちます。
さらに、上司や同僚からのフィードバックを受けることで、自身では気づきにくい強みや改善点を把握できるため、職場環境の適応にもつながります。
企業側としては、定期的な面談やキャリアカウンセリングを導入し、社員が自身の特性を理解しやすい環境を整えることが、長期的な雇用の安定につながるでしょう。
まとめ:ADHDの特徴を理解すれば生産性につなげることも
ADHDの特性は、業務の進め方や職場環境に影響を与えることがありますが、適切な対応を講じることで強みに変えることが可能です。
創造力や行動力を活かせる職務に配置し、タスク管理の工夫や合理的配慮を取り入れることで、パフォーマンスを最大化できます。
企業側がADHDの特性を正しく理解し、適材適所の環境を整えることは、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。
「法定雇用率を満たせない」
「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、
障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、
ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。
サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。