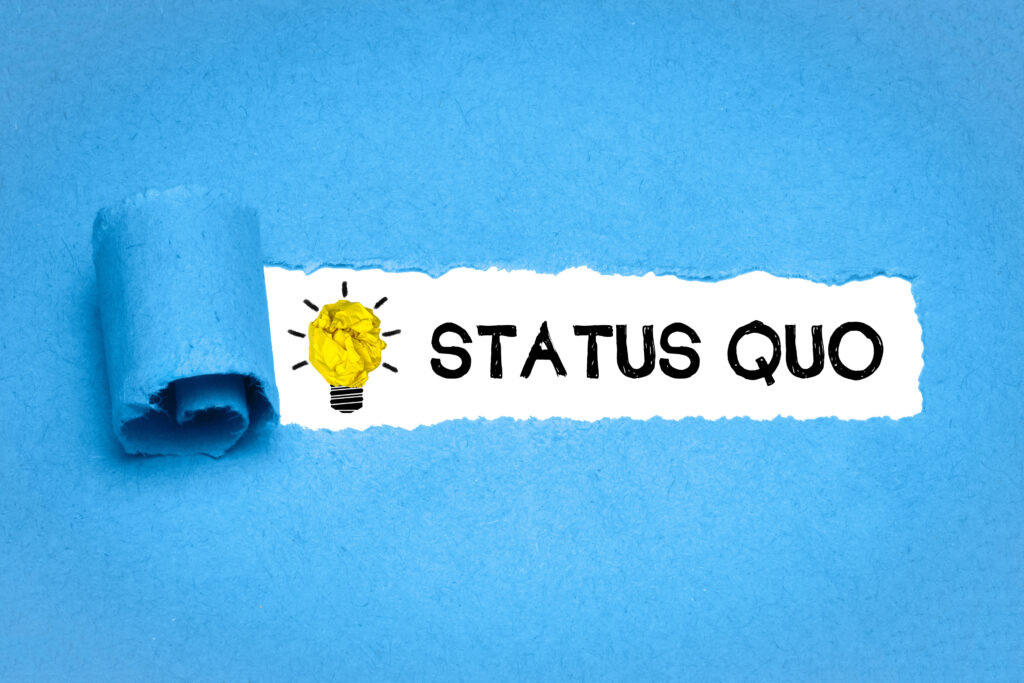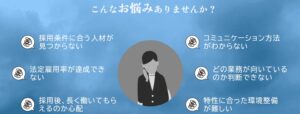中小企業の経営者にとって、発達障害のある方の雇用状況や他社の取り組み事例は、今後の人材戦略を考える上で重要な情報です。
本記事では、最新の統計データに基づき、発達障害者の雇用状況や傾向を解説。
また、障害者雇用促進法の概要や関連する助成金制度、支援機関の活用方法についても紹介します。
中小企業で発達障害者を雇用するメリットや成功事例、職場定着のポイントも取り上げ、経営判断に役立つ視点を記載しますので参考にしてください。

発達障害者の雇用状況:最新統計と全体傾向
地域的に見ると、関西地域では障害者雇用の意識が比較的高く、主要府県の実雇用率は全国平均を上回っています。
例えば奈良県では実雇用率が2.88%に達し全国平均を大きく上回っています。
一方で大阪府は2.21%(※当時)と関西内では最も低かったものの、前年から0.09ポイント増加しており増加幅ではトップクラスでした。
この背景には、大阪府が2010年に施行した「大阪府障害者等の雇用促進等と就労の支援に関する条例」(ハートフル条例)の効果があると考えられます。
条例により府の入札参加企業に障害者雇用状況の報告を義務づけ、不足があれば罰則規定も設けるなど独自の施策が推進されました。
直近の大阪府の状況を見ると、2024年6月時点で大阪府内の民間企業における障害者雇用者数は前年より6.4%増の62,038人となり、21年連続で過去最高を更新しました。
なかでも精神障害者の雇用は前年比18.6%増と顕著な伸びを示しており、発達障害者の増加が雇用者数押し上げの一因と考えられます。
大阪府の実雇用率は2.44%に上昇しましたが、2024年4月に民間企業の法定雇用率が2.5%へ引き上げられたため未達成状態であり、法定雇用率を達成している企業の割合も41.7%と前年の46.1%から低下しました。
特に中小企業での達成率低下が影響しており、法定率引き上げに中小企業が追いついていない現状が伺えます。
企業規模別に見ると、大企業ほど障害者雇用が進んでおり、中小企業では遅れがち。
大阪府の例では、従業員1,000人以上の企業では6割以上が法定雇用率を達成していますが、1,000人未満では達成企業は35~40%程度に留まっています。
このように企業規模が小さくなるほど障害者を雇用していない企業の割合が高い傾向があります。
ただし、小規模企業の中にも障害者雇用に積極的に取り組み成果を上げている例(後述の成功事例参照)もあり、支援策の活用次第で発達障害者の雇用は中小企業でも十分可能です。

(出典:出典:Challeng LAB 障碍者の雇用 年齢階級別)
障害者雇用促進法の概要と企業の責任
障害者雇用促進法は、企業に対して障害者の雇用機会を促進し、その職業の安定を図ることを目的とした法律です。
特に重要なのが法定雇用率制度で、従業員に占める障害者の割合が一定以上になるよう企業に義務付けています。
民間企業の場合、2024年4月に法定雇用率が従来の2.3%から2.5%に引き上げられました。さらに2026年7月には2.7%へ段階的に引き上げることが予定されています。
これは労働者約40人につき1人以上の障害者を雇用する計算で、企業規模によりますが概ね常用労働者43.5人以上(実質的に45人程度)いる企業は法定雇用率に相当する障害者を雇用する義務があります。
法定雇用率の算定対象となる「障害者」には、身体障害者、知的障害者、精神障害者が含まれます。
精神障害者にはASD(自閉スペクトラム症)やADHDなどの発達障害も含まれており、2018年の法改正で精神障害者(=発達障害者を含む)の雇用が企業の義務に加わりました。
これにより、2018年以降は発達障害のある人も企業の法定雇用率のカウント対象となり、各企業で雇用が進んだ経緯があります。
一方で、発達障害者の多くは見た目では障害と分かりにくいことや、コミュニケーション面の特性から受け入れ側の職場で配慮が必要なケースも。
そのため、障害者差別解消法(2016年施行)に基づき、企業は障害を理由とする不当な差別的扱いの禁止や合理的配慮の提供義務を負っています。
例えば、発達障害のある社員に対して業務指示を紙で渡す、静かな集中できる作業スペースを設けるなどの配慮は、企業に求められる取り組みです。
企業に課せられる罰則とインセンティブ(納付金制度)
障害者雇用促進法では、一定規模以上の企業に対し、法定雇用率を達成できない場合のペナルティ制度と、達成・超過した場合のインセンティブ制度が用意されています。
常用労働者100人を超える規模の企業が法定雇用率を未達成の場合、不足する障害者1人あたり月額5万円(年間60万円)の「障害者雇用納付金」を国に納める必要があります。
集められた納付金は財源として、法定雇用率を達成または上回っている企業への調整金・報奨金に充てられます。
具体的には、法定雇用率を達成した企業には、従業員100人超の事業主で障害者1人あたり月額2万9,000円、従業員100人以下の事業主で同2万1,000円が支給されます。
また、法定雇用率を上回る人数を雇用している場合には、その超過人数に応じて障害者雇用調整金(原則1人当たり月額27,000円)が支給されます。
反対に、従業員規模が小さい企業(100人以下)であっても、自主的に多くの障害者を雇用している場合には報奨金が支給される仕組みです。
この納付金制度により、「雇用していない企業から雇用している企業へ」資金が循環し、中小企業でもコスト面の不安を和らげながら障害者雇用に取り組めるようになっています。
さらに、2018年の精神障害者雇用義務化に合わせて特例措置も導入されました。
例えば、通常は0.5人計算となる短時間労働(週20~30時間)の精神障害者について、雇用開始から3年以内かつ手帳取得から3年以内であれば1人分としてカウントする特例が設けられました。
当初この特例は時限措置(5年間)でしたが、2023年4月以降は期間を定めず延長されています。
また2024年8月からは、週10~20時間勤務の重度障害者(身体・知的・精神)も0.5人として算定できるよう緩和されています。
これらの措置は、短時間勤務しかできない人でも企業が受け入れやすくする工夫であり、発達障害者を含む精神障害者の雇用機会拡大につながっています。
発達障害者の雇用に活用できる助成金・支援制度
発達障害のある方を雇用する企業向けに、国や自治体は様々な助成金・支援制度を用意しています。
これらを上手く活用することで、中小企業でも発達障害者の採用・定着に伴う負担を軽減できます。
代表的な制度をいくつか紹介します。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難病の方をハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主に支給される助成金です。
障害者手帳を持たない発達障害の方でも対象となり、継続雇用して6か月経過後に支給を受けられます。
支給額は労働時間や企業規模によって異なりますが、中小企業の場合、最大120万円(2年間合計)程度の助成を受けることができます。
障害者トライアル雇用助成金
発達障害者や精神障害者を試行的に雇用する際に活用できる助成金です。
例えば、週20時間以上の勤務が難しい方に対して、将来的に20時間以上の勤務を目指して最大3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)を行う場合に支給されます。
企業はこの制度を使って本人の適性や職場適応を見極めながら雇用でき、助成金によって試行期間中の人件費負担が一部補填されます。
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援
発達障害者の職場定着を図るため、専門のジョブコーチによる支援を受けられる制度です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「地域障害者職業センター」などを通じて、ジョブコーチが企業と障害者の間に入り、現場での業務習得や環境調整を支援します。
ジョブコーチの派遣費用については公的に負担される部分が大きく、企業にとっては低コストで専門的な定着支援を得ることができます。
また、企業自らが社内にジョブコーチ役を置く場合に活用できる障害者雇用安定助成金(中小企業障害者支援員配置助成など)もあります。
障害者雇用に伴う設備等の助成
発達障害者が働きやすい職場環境を整えるための助成も用意されています。
例えば、執務室のレイアウト変更や防音設備、照明の調整装置など、合理的配慮の提供に必要な設備投資に対し助成金が出る場合があります(障害者雇用安定助成金の「障害者職場環境適応改善コース」等)。
これにより、中小企業でも職場環境の整備を進めやすくなります。
以上のような助成金・支援策を活用することで、企業は発達障害者の雇用に伴う初期コストやリスクを軽減できます。
特にハローワーク等の公的機関と連携すれば最新の支援制度情報を得られるため、積極的に相談・活用すると良いでしょう。
発達障害者を雇用するメリットと中小企業の成功事例
発達障害のある人材を雇用するメリットは、多くの企業で認識され始めています。
経営者の視点から押さえておきたい主なメリットは次のとおりです。
法令遵守と企業イメージ向上
発達障害者を含む障害者雇用を進めることで、法定雇用率を達成し納付金の負担を回避できます。
法令遵守は企業のコンプライアンス評価を高め、社会的信用の向上につながります。
また、多様な人材を受け入れる企業文化は社内外へのイメージアップとなり、CSR(企業の社会的責任)を果たす取り組みとして評価されます。
戦力となる独自の強みの活用
発達障害のある方は、特定の分野で優れた集中力や記憶力、正確性を発揮するケースがあります。
例えば、自閉スペクトラム症(ASD)の方はルーチン作業やデータチェック、プログラミング、デザインなどで高い精度の仕事をすることがあります。
また、注意欠如・多動症(ADHD)の方は発想力や行動力に優れ、企画職などで新たな視点をもたらすこともあります。
このように人によって際立つ強みを業務にマッチさせることで、生産性向上や新たな価値創出に寄与します。
定着すれば安定した人材に
発達障害者は一度職場になじみ、自分の得意分野で役割を得られれば、長期にわたり安定して勤務してくれる傾向があります。
後述するように定着率も比較的高く、戦力化できれば中核人材として活躍が期待できます。
特に中小企業では人材の流出が事業継続リスクとなるため、ミスマッチを防いで採用できれば高い忠誠心・継続勤務が得られるでしょう。
職場の多様性促進と社員の成長
発達障害者を受け入れる過程で、職場全体のコミュニケーションの見直しや業務フローの改善が促されることがあります。
例えば、あいまいだった指示を明確化したり、属人的だった業務をマニュアル化したりといった工夫が進み、結果的に職場の生産性向上につながるケースもあります。
また、多様な同僚と働く経験は社員の人間的成長やチームワーク向上に寄与し、社内の風通しが良くなるとの指摘もあります。
中小企業での成功事例(大阪含む)
実際に発達障害者の雇用で成果を上げている中小企業の事例を2つ紹介します。
製造業A社(従業員約120名、京都府)
金属機械の製造を行うA社では、法定雇用率を達成するため初めて精神・発達障害のある人の採用に踏み切りました。
京都府の支援機関と連携し、候補者を職場実習で受け入れて職務適性を見極めた上で採用しています。
同社には受注生産に伴う細かな組立・検査作業があり、そこで発達障害のある社員が持ち前の集中力と几帳面さを発揮しました。
ライン作業外の繰り返し業務など自分のペースで取り組める作業を担当させたところ、生産品質の向上に寄与し、周囲の社員からも信頼を得ています。
結果としてA社は障害者の職場定着に成功し、現在は3名の障害者を安定雇用しています。「障害者の得意分野を活かせる業務切り出し」と「支援機関との連携によるマッチング」が成功のポイントでした。
IT企業B社(従業員300名規模、大阪府)
大阪に本社を置くIT系中小企業B社では、システムテストやデータ分析業務に発達障害のある人材を積極的に起用しています。
きっかけは、テスト業務の精度向上と人材不足の解消策として、発達障害者の高い集中力に注目したことでした。
B社は専門の人材支援会社と協力し、ASD傾向の人材を複数採用。入社後はセミナー形式でサイバーセキュリティ研修を施し、短期間で業務スキルを習得させました。
その結果、彼らはソフトウェアのバグ検出やサイバー攻撃の監視といった分野で「天然のハッカー」とも称される卓越した能力を発揮し、B社の新たな戦力となっています。
この取り組みは社内でも成功事例として評価され、経済産業省出身の専門家を招いて特例子会社の設立(障害者雇用に特化した子会社)も視野に入れるなど、事業拡大につながっています。
B社の事例は、発達障害者の強みをコア業務に活かすことでビジネス上の成果を上げた好例と言えるでしょう。
上記のように、中小企業でも発達障害のある社員が戦力となり得ることが分かります。
成功の共通点は、発達障害者の特性を正しく理解し、それを活かせる業務や役割を用意したこと、そして外部の支援リソースを上手に活用したこと。
経営者としては「どのような仕事ならその人の能力が発揮できるか」「社内に受け入れ態勢を整えるには何が必要か」を考え、支援機関の知恵も借りながら計画的に進めることが大切です。
発達障害者の職場定着率と定着支援のポイント
採用した発達障害者に長く働いてもらうためには、職場定着率にも注目する必要があります。
厚生労働省のデータによれば、障害者枠で就職した場合の発達障害者の1年後職場定着率は約79.5%と報告されています。
この数字は、知的障害者(75.1%)、身体障害者(70.4%)よりも高く、発達障害者は比較的定着しやすい傾向にあることを示しています。
発達障害者の場合、自身の特性に合った仕事に就ければ高いモチベーションを維持しやすく、企業にとって貴重な人材となりうるのです。
一方、精神障害者(発達障害以外)の1年後定着率は49.3%程度と低めで、精神疾患特有の体調変動などもあり離職率が高い傾向があります。
発達障害者の定着率がそれらより高いとはいえ、油断せず適切なフォローを行うことが重要です。
定着支援のポイントとして、まずミスマッチを防ぐ採用が挙げられます。
採用段階で「本人の強みが発揮できる業務か」「無理なく続けられる環境か」をしっかり見極めることが肝要。
可能であれば面接だけでなく職場体験や実習の機会を設け、適性をお互い確認するのが望ましいでしょう。
また、発達障害のある方本人にも自己理解を深めてもらい、自身の配慮事項や得意不得意を雇用先に適切に伝えてもらうことも長く働くための要素です。
入社後のフォローでは、以下のような取り組みが効果的です。
明確な業務指示とフィードバック
発達障害のある社員には、曖昧な指示や場の空気を読むことを求める状況は負担になります。
業務の手順や期待する成果を具体的に伝え、指示は口頭だけでなく書面やチェックリストで補足するなど工夫しましょう。
定期的なフィードバック面談を行い、困り事がないかヒアリングすることも定着支援につながります。
職務の工夫(業務切り出し)
前述の事例にもあったように、適材適所の仕事配分が定着の鍵です。
発達障害者に任せる業務は、本人の得意を活かせる内容にし、苦手分野はサポートや他メンバーとの分担で補いましょう。
「会社に適当な仕事があるか」が企業側の大きな課題であるとの調査結果もあり、業務マッチングが定着率を左右します。
職場内サポート体制
配属先の上司や先輩にあたる社員への事前教育も有効です。
発達障害への正しい理解を深めてもらい、指導役の社員にはサポートのポイントを共有します。
場合によってはメンター制度(相談役となる先輩を1対1でつける)を導入し、業務以外の相談もしやすい関係を築くと安心感が生まれます。
また、人事部門や産業医と連携し、定期面談や健康チェックを行うことで早期に不調を察知し手を打てます。
外部リソースの活用
前述のジョブコーチ支援や、地域の「障害者就業・生活支援センター」との連携も活用しましょう。
障害者就業・生活支援センターでは、職場定着に向けた企業と本人双方への相談支援を継続的に行っています。
必要に応じて第三者の視点で職場環境を見直したり、家族とも連携して生活面の安定を図ったりすることで、退職のリスクを下げることができます。
発達障害者の雇用に活用できる支援機関と利用方法
発達障害者の雇用を成功させるには、企業単独で抱え込まず、専門の支援機関を上手に利用することが重要です。
以下に主な支援機関とその活用方法を解説します。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、一般就労を目指す障害のある方に職業訓練や就活サポートを提供する福祉サービスです。
発達障害のある方も多く利用しており、ビジネスマナー研修やPCスキル訓練、企業実習などを経て就職準備を行っています。
企業側から見ると、これら事業所と連携することで適性のある人材を紹介してもらえるメリットがあります。
例えば大阪府内にも発達障害者に特化した就労移行支援事業所が複数あり、人材ニーズを伝えることでマッチする候補者を推薦してもらえます。
また、就労移行支援事業所の利用者を受け入れて職場実習を行えば、採用前に実際の業務適応度を見ることができます。
採用後も事業所の職員が定着支援でフォローしてくれるケースも多く、特に初めて発達障害者を雇用する中小企業にとって心強いサポーターとなるでしょう。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークには「障害者専門窓口」や担当者が配置されており、発達障害者を含む障害者雇用のマッチング支援を行っています。
企業はハローワークに障害者求人を登録することで、就職を希望する発達障害のある求職者を紹介してもらえます。
ハローワークは応募前職場見学会や合同面接会などイベントも開催しており、発達障害者と企業が出会う機会を提供しています。
また、ハローワーク経由で採用した場合、前述の各種助成金(特定求職者雇用開発助成金など)の手続きもスムーズに進められます。
さらに、ハローワークには障害者職業カウンセラーが在籍しており、企業向けに職場環境整備のアドバイスや困ったときの相談対応も行っています。
無料の公的サービスですので、積極的に活用すると良いでしょう。
特例子会社制度
特例子会社とは、親会社が100%出資して設立し、一定数以上の障害者を雇用する子会社のことです。
厚生労働大臣の認定を受けることで、その子会社で雇用する障害者を親会社グループ全体の雇用率に算入できます。
多くは大企業グループでの活用事例ですが、中堅規模の企業でも複数社で共同出資して特例子会社を設立するケースがあります。
大阪府でも特例子会社の設立支援を行うコンサルティングや助成が用意されており、雇用率達成と障害者の安定就労の両立を図れます。
ただし特例子会社の設立・運営には相応のノウハウとコストが必要なため、中小企業の場合はまず既存の特例子会社への業務委託(例:特例子会社に清掃業務やデータ入力業務を委託し障害者が従事)などから検討する方法もあります。
親会社としてではなくとも、地域の特例子会社をパートナーとして活用することで、自社単独では難しい障害者の活躍機会を創出できます。
その他の支援機関
上記以外にも、各都道府県には「障害者職業センター」や「障害者就業・生活支援センター」が設置され、企業と障害者双方への幅広い支援を提供しています。
例えば大阪府では、ハートフル条例に基づき法定雇用率未達成の中小事業主(従業員40~100人規模、府内のみ事業所)に対して雇用計画の提出を努力義務とし、きめ細かな支援を行っています。
この一環で府は「障がい者サポートカンパニー」制度を設け、中小企業への専門家派遣や人材紹介を進めています。
民間の人材紹介会社やコンサルティング会社でも、発達障害者雇用のサポートサービスを提供するところが増えてきました。
自社だけで解決が難しい課題は、こうした外部機関に相談・連携することで解決策を見出せる場合があります。
まとめ:発達障害の方を雇用している企業の割合は増える可能性がある
発達障害者の雇用促進は、企業経営にとって新たなチャレンジかもしれませんが、同時に戦力確保と職場多様化のチャンスでもあります。
最新の統計は発達障害者の雇用者が大きく伸びている現実を示しており、今後は中小企業にもその波が本格的に押し寄せるでしょう。
法制度や支援策が整いつつある今、経営者として正しい知識と積極的な姿勢で取り組めば、自社にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。
ぜひ、自社で「発達障害のある人が活躍できる場」を育み、企業価値向上につなげていただきたいと思います。
株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。
「法定雇用率を満たせない」
「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、
障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、
ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。
サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。
-300x118.jpg)