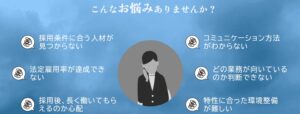本記事では、障がい者雇用枠で働く社員の平均勤続年数に焦点を当て、その実態と課題を探ります。
特に発達障がい(ADHD)のある社員に注目し、平均勤続年数が短くなりがちな理由や背景を解説。
また、平均勤続年数が長い企業に共通する特徴や取り組み事例を、関西地域の有名企業・中小企業のケースも交えながら紹介します。
障がい者雇用枠と平均勤続年数の基礎知識
法定雇用率と障がい者雇用枠の概要
企業に課せられる障がい者雇用の義務は、「障害者雇用促進法」に基づき一定の割合(法定雇用率)の障がい者を雇用することです。
現在、民間企業の法定雇用率は2.3%(従業員43.5人に1人以上)ですが、2026年に向け順次引き上げが予定されており、2024年度には2.5%、2026年度には2.7%へと拡大します。
また、雇用義務の対象となる企業規模も段階的に広がり、従業員数40人以上(2024年4月~)、37.5人以上(2026年7月~)へと拡大される予定です。
このような制度の下で、多くの企業が「障がい者雇用枠」を設けて人材採用を行っており、障がい者雇用枠とは障がい者手帳を持つ方を対象とした特別な採用枠のことを指します。ここで採用された社員は、一般枠の社員と異なる勤務条件や配慮を受けながら働くケースもありますが、企業にとって重要な戦力であり、近年その数は年々増加しています。
実際、厚生労働省の最新集計(令和5年6月時点)によれば、民間企業で雇用されている障がい者数は64万2,178人で前年より約2万8千人増加し、20年連続で過去最高を更新しました。
特に精神障がい者(発達障がい者を含む)の雇用者数が前年から18.7%増と大幅に伸びており、法定雇用率への対応や社会の理解進展に伴い、障がい者雇用枠で働く人々が着実に増えている状況です。
平均勤続年数と定着率とは何か
平均勤続年数とは、ある企業や区分において社員がどのくらい長く勤務しているかの平均値を指し、社員の定着度合いを測る重要な指標です。
一方で定着率とは、採用後一定期間(例えば1年後)に在職している割合を示す指標。
障がい者雇用において平均勤続年数や定着率が注目されるのは、長く働き続けられる職場環境かどうかを示すからです。
勤続年数が長ければ、社員が職場に満足し能力を発揮し続けている可能性が高く、一方で勤続年数が極端に短かったり定着率が低かったりする場合、何らかの課題(ミスマッチや職場環境上の問題等)が潜んでいると考えられます。
障がい者雇用枠で働く社員の場合、仕事や職場への適応に支援が必要なケースも多いため、企業としては単に雇用数を満たすだけでなく「いかに長く安定就業してもらうか(定着してもらうか)」が重要なテーマとなります。
障がい者雇用の現状データ:障がい種別ごとの勤続年数
障がい者雇用の状況を把握するため、まず障がい種別ごとの平均勤続年数を見てみましょう。
厚生労働省が5年ごとに実施する「障害者雇用実態調査」の結果によれば、直近の令和5年度調査(2023年実施)において、障がい者全体の平均勤続年数は以下のようになっています。
| 年度 | 身体障がい者 | 知的障がい者 | 精神障がい者(発達障がい者含む) |
|---|---|---|---|
| 1998年 | 約11年0か月 | 約8年0か月 | 約3年0か月 |
| 2003年 | 約11年2か月 | 約8年2か月 | 約3年1か月 |
| 2008年 | 約11年4か月 | 約8年4か月 | 約3年2か月 |
| 2013年 | 約11年6か月 | 約8年6か月 | 約3年3か月 |
| 2018年 | 約11年10か月 | 約8年8か月 | 約3年4か月 |
| 2023年 | 約12年2か月 | 約9年1か月 | 約5年3か月 |
障害者の平均勤続年数(厚生労働省「障害者雇用実態調査」より)
※1998年~2023年の推移データ。
身体障害者・知的障害者は長期的に平均勤続年数が長い一方、精神障害者(発達障害者含む)は他の区分より短く、近年やや伸びてきているものの依然低水準に留まる。
上記のデータから読み取れるように、身体障がい者の平均勤続年数は最も長く、2023年時点で「約12年2か月」に達しています。
次いで知的障がい者が「約9年1か月」となっており、長期にわたり安定して働くケースが多いことが伺えます。
一方で精神障がい者(発達障がい者を含む)の平均勤続年数は「約5年3か月」と他の区分に比べて大きく短い水準にあります。
これは裏を返せば、精神・発達障がいのある社員の中には比較的最近雇用が始まった人が多い(勤続年数が浅い人が多い)ことや、職場に定着できず離職する割合が高いことを示唆します。
実際、2018年時点の同調査(平成30年度)でも精神障がい者の平均勤続年数は約3年2か月、発達障がい者は約3年4か月と報告されており、5年前と比べるとやや改善はしているものの、依然として勤続年数の短さが課題となっている状況です。
発達障がい(ADHD)社員の平均勤続年数と離職要因
発達障がい社員の平均勤続年数の実態
発達障がい者(主にADHDなどを含む)の平均勤続年数は他の障がい種別より短い傾向にあります。
平成30年度の障害者雇用実態調査では、発達障がい者の平均勤続年数は約3年4か月であり、これは身体障がい者(約10年2か月)や知的障がい者(約7年5か月)と比べて大幅に短い結果でした。
この数値は発達障がい者の雇用が本格化した当初の状況を示しており、「3年程度で離職してしまうケースが多い」ことを意味しています。
一方、直近の令和5年度(2023年)のデータでは、発達障がい者の平均勤続年数は約5年1か月まで延びています。
この背景には、2018年に精神障がい者の法定雇用義務化が始まって以降、企業側のノウハウ蓄積や支援体制の強化により徐々に定着率が改善してきたことが考えられます。
実際、様々な企業で障がい者雇用の取り組みが進む中で、全体として障がい者の平均勤続年数は伸びる傾向にあります。
しかしそれでもなお、発達障がい者の勤続年数は他区分に比べ低い水準に留まっており、企業にとって発達障がい者の長期就労をいかに実現するかが重要な課題であると言えます。
発達障がい者と他の障がい者の定着率の比較
勤続年数と関連して、定着率のデータも確認してみましょう。
とりわけ、採用後1年後の定着率は、その社員が職場環境に適応できたかの指標になります。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 傘下の障害者職業総合センターが行った調査(2017年公表)によれば、就職1年後の職場定着率は発達障がい者で71.5%と、知的障がい者(68.0%)、身体障がい者(60.8%)を上回り最も高い水準でした。
一方、精神障がい者(発達障がい以外の精神疾患を含む)の1年後定着率は49.3%と半数を下回っており、精神障がい者全体では定着が特に難しい状況が浮き彫りとなっています。
発達障がい者の1年定着率が比較的高いことについて、専門家は「障がい者枠での就職により周囲の理解や配慮を受けられれば、しっかり職場に根付く傾向がある」ためではないかと分析しています。
これは、適切なサポートがあれば発達障がいのある社員も短期で辞めず定着しやすいことを示すデータと言えます。
ただし、1年後に定着していてもその後長く勤め続けられるかは別問題。
発達障がい者の平均勤続年数が5年程度に留まる現状からすると、中長期的には離職するケースが多いことが示唆されます。
発達障がい社員の勤続年数が短くなりがちな理由
発達障がい(ADHD)のある社員の勤続年数が短くなる背景には、本人側と職場環境側双方の要因が絡んでいます。
まず本人側の要因として、ADHDの特性から職場でストレスを感じやすいことが挙げられます。
具体的には、
「指示を忘れてしまう」
「ケアレスミスが多い」
「同時に複数の業務を捌くのが難しい」
といった困難さから、周囲の期待に応えられないと感じ自己評価が下がるケースがあります。
また、過集中やこだわりの強さゆえに周囲とペースが合わず孤立したり、逆に興味が持てない業務には集中できず生産性が上がらないというミスマッチも起こりえます。
こうした状態が続くと、当事者は強い不安やストレスを抱え、メンタルヘルス不調(二次障害)に陥ってしまうこともあります。
結果的に「自分にはこの職場で働き続けるのは難しい」と感じて退職を選択してしまうケースが少なくありません。
一方、職場環境側の要因としては、障がい特性への理解不足と業務内容のミスマッチが大きな理由として指摘できます。
多くの企業では発達障がい者の雇用経験が浅く、現場では「どのように接したら良いかわからない」「配慮すべきポイントが掴めない」といった戸惑いがあります。
実際、パーソル総合研究所の調査では、精神・発達障がい者の雇用について「ノウハウが蓄積途中」「手探り状態だ」と感じている企業が57.0%にも上ることが明らかになっています。
周囲が適切にサポートできないままでは、せっかく採用しても働きづらさが解消されず離職につながってしまいます。
また、障がい者枠で採用された発達障がい者の場合、企業によっては配慮のつもりで業務内容が単調で簡単すぎる配置をされることがあります。
確かに過度な負担を避ける意図は理解できますが、あまりに簡単すぎる仕事ばかりでは本人の成長実感が得られずモチベーション低下を招く恐れがあります。
実際のアンケートでも、障がい者雇用枠で働く精神・発達障がい者から「教育・研修の機会が少ない」「仕事が簡単・単調すぎる」といった成長機会の乏しさへの不満が多いことが報告されています。
その結果、「このままここで働き続けてもスキルアップできない」と感じ退職してしまうケースも考えられます。
平均勤続年数が長い企業に共通する特徴
職場環境の整備とサポート体制の充実
平均勤続年数が長い企業の第一の特徴は、障がいのある社員が働きやすい職場環境を整備し、手厚いサポート体制を敷いていること。
入社時から定着まで一貫して支援できるよう、人事部門と現場部門が連携してフォローする仕組みを持っています。
ある企業では人事部に「定着支援担当者」を置き、発達障がいのある社員の業務指導や相談対応について現場管理者をサポートしています。
現場任せにせず人事と連携することで、問題の早期発見と対策立案が可能となり、本人の不安を迅速に解消できます。
また、社外の専門機関とも協力し、ジョブコーチ(職場適応援助者)を活用する企業も多く見られます。
ジョブコーチは、障がい者本人と職場との橋渡し役として機能し、本人の特性やコミュニケーション方法を職場に伝えたり、困ったときに双方から相談を受けることでミスコミュニケーションを防ぎます。
大企業だけでなく中小企業でも、地域の障害者職業センター等と連携してジョブコーチ支援を受けながら定着を図るケースが増えています。
少しずつ業務に慣れてもらう工夫として、入社当初は短めの勤務時間からスタートし、体調管理をしやすくした上で徐々にフルタイムに近づけるなど柔軟な勤務形態を採用する企業もあります。
このように、会社全体でサポートする仕組みを整えている職場では、発達障がいのある社員も安心感を持って働き続けることができ、結果的に勤続年数の延伸につながっています。
社内理解と障がいに対する教育の徹底
二つ目の共通点は、社員全体の障がいに対する理解促進に力を入れていることです。
発達障がい者が長く働ける企業では、配属部署のメンバーだけでなく会社全体で定期的な勉強会や研修を開催し、ADHDやASDなど発達障がいの特性や配慮事項について教育しています。
現場の同僚が障がい特性を理解していれば、例えばミスが発生した際にも「なぜ起こったのか」「どう対処すれば再発防止できるか」を一緒に考えることができます。
ある大阪の企業では、精神・発達障がい者を初めて受け入れる際に大阪障害者職業センターの専門家を招き、現場担当者向けの説明会を実施しました。
その場で障がいの特性や具体的な配慮方法を学んだことで、「どう接して良いかわからない」という不安が解消され、現場社員の協力体制が強化されたといいます。
また別の企業では、社内報や朝礼で障がい者社員の活躍を紹介し、社員一人ひとりが「共に働く仲間」として自然に受け入れる風土づくりを行いました。
その結果、「障がいのある方もいて当然で、特別扱いではなく世の中の縮図に近い自然な会社になった」と語られています。
このように、社内の偏見や遠慮を取り除き、オープンにコミュニケーションできる環境を作ることが、長期定着の大きな要因となります。
適性に合わせた業務配置とキャリア支援
平均勤続年数が長い企業の三つ目の特徴は、社員各人の適性や強みに合わせた業務配置とキャリア形成支援を行っている点です。
発達障がいのある社員と一口に言っても、その得意不得意は人それぞれです。
ある企業では、発達障がいのある社員を採用する際に2週間の実習インターンを事前に行い、実際の職場で働いてもらいながらお互いに適性を見極めるプロセスを取り入れました。この実習を経て社員自身も職場の雰囲気に慣れることができ、企業側も適切な業務を割り当てる判断材料を得られたことで、採用後のミスマッチを防ぐことに成功しています。
また、京都に本社を置くある製薬企業では、知的障がい・発達障がいのある社員を採用する際、入社後すぐ現場配属せず一度人事部付とし、ビジネスマナーや仕事の姿勢を学ぶ期間を設けています。
その上で、社内で様々な部署の仕事を経験するジョブローテーション的な社内インターンを行い、最適な配属先を見極めてから正式に部署配属するという丁寧な方法を採っています。
このように時間をかけて適所適材を図ることで、本人にとって無理なく力を発揮できるポジションで働けるため、やりがいを持って長く勤務しやすくなります。
一部の企業では障がい者社員にも定期的な目標設定や研修機会を与え、昇進・昇格の道も開いています。
障がいの有無に関わらず「成長したい」という意欲を尊重し、努力すればステップアップできる環境を用意することが、ひいては本人のモチベーション維持と長期就労につながっています。
関西のあるIT企業は発達障がいの社員に対し、最初は補助的業務から始めつつも本人の興味や熱意を見て専門職への道を開く柔軟な対応を取り、「技術より可能性――興味が拓くSEへの道」という形でエンジニア職に挑戦させたケースもあります。
この社員は自らの「成長したい」という意欲が背中を押し、数年かけて一人前の戦力として活躍するに至りました。
このように、本人の強み・興味と仕事をマッチングさせ、成長を後押しする企業は、平均勤続年数が長い傾向にあります。
柔軟な働き方の導入と合理的配慮の徹底
四つ目の特徴は、柔軟な働き方を認め、必要な合理的配慮を徹底していることです。
発達障がいを含む精神障がいのある社員は、体調やコンディションの波が健常者以上に大きい場合があります。
例えば、ストレスや睡眠リズムの乱れから体調不良になったり、薬の副作用で一時的にパフォーマンスが落ちることも。
平均勤続年数の長い企業では、そうした特性を踏まえて就業規則や制度面で柔軟な対応を可能にしています。
突発的な休暇や通院が発生しても有給休暇とは別枠で病気休暇を取得できる制度を設けたり、リモートワークや時差出勤を認めて本人のペースで働ける環境を整えたりしています。
大阪府など自治体でも「精神・発達障がい者の多様な働き方促進」として短時間勤務制度や在宅勤務の導入企業を支援する事業が行われており、そうした制度を積極的に活用する企業ほど定着率が高まる傾向があります。
加えて、職場でのコミュニケーション方法の工夫も重要な配慮ポイント。
ADHDの社員に対しては、口頭指示だけでなくマニュアルやチェックリストを用意する、タスク管理ツールを使って視覚的にスケジュールを示すなどの配慮が有効です。
また、ASD傾向がある社員には、急な予定変更を極力避け、業務手順をできるだけ明文化しておくと安心して作業できます。
平均勤続年数が長い企業では、こうした個々の障がい特性に応じた配慮措置を講じることで、社員が無理なく能力を発揮できる環境を維持しています。
その結果、本人が「会社から必要な配慮が得られている」と実感でき、精神的にも安定して働き続けられるのです。
事実、とある調査によれば、精神障がい者が「働く幸せ」を感じられない要因のトップに「障害や特性に対する周囲の理解が得られないとき」(51.0%)や「会社から必要な配慮が得られないとき」(50.0%)が挙げられており、逆に言えば理解と配慮が得られる職場では働きがいが向上し長期就業につながることが示唆されています。
柔軟な働き方の導入と合理的配慮の徹底こそが、平均勤続年数を延ばす企業の大きな支柱となっています。
定期的な面談・フォローアップとチーム支援
五つ目に挙げられる特徴は、定期的な面談やフォローアップを行い、チームで支える体制があることです。
勤続年数が長い企業では、発達障がいのある社員に対してきめ細かなコミュニケーションを欠かしません。
入社直後だけでなく、その後も定期的に人事担当者や指導担当者が面談を行い、業務の進捗や困りごとをヒアリングします。
そこで出た課題については、社内関係者が一堂に会して解決策を検討する場を設けます。
例えば、ある会社では発達障がいの社員との面談に人事担当・現場上司・ジョブコーチ・支援機関の担当者が集まり、「どうすれば定着できるか」をチームで議論しました。
一人ひとり課題が異なる中、様々な視点から意見を出し合うことで的確な支援策を打てたといいます。
こうしたチーム支援アプローチによって、現場担当者の負担も軽減され、社内にノウハウが蓄積されていきます。
また、同僚社員とのペア作業やメンター制度を導入する企業もあります。
聴覚障がいの社員には手話のできる社員とペアで作業させた事例がありますが、発達障がいの社員においても面倒を見てくれる先輩社員がいるだけで困りごとを相談しやすくなり、孤立を防ぐことができます。
発達障がいの特性上、時折フィードバックの伝え方にも工夫が必要です。
叱責よりも具体的に良かった点・改善点をフィードバックし、必要に応じて紙に書いて視覚化して伝えるなどの方法も効果的です(実際、長く活躍しているADHD当事者からは「何か起きたとき、気持ちを紙に書いて整理する」というセルフケア方法が紹介されています)。
企業側も同様に、問題発生時に感情的にならず客観的に状況を整理し、建設的な対話を心がけることが、信頼関係を損なわず長期に働いてもらうコツと言えます。
平均勤続年数が長い企業の具体例(関西編)
大企業の事例:関西拠点の有名企業における取り組み
関西地域には、障がい者雇用に積極的に取り組み、発達障がい者を含む社員の定着実績が高い企業が多数存在します。
西尾レントオール株式会社(総合レンタル業)
大阪に本社を置く西尾レントオール株式会社(総合レンタル業)では、20年以上前から障がい者雇用を進め、現在全国の営業所で約30名、本社事務部門で2名の障がい者社員が働いています。
そのうち発達障がいのある社員Bさん(事務職)は、入社前にエンカレッジ社(就労移行支援事業所)と連携して2週間の職場実習を経て採用されました。
西尾レントオールではそれまで発達障がい者の受け入れ経験がなく不安もあったそうですが、実習を通じてお互い理解を深め、「新しい人が入ることで社員が気遣いや協調の姿勢を見せ、職場に和やかな空気と適度な緊張感が生まれた」といいます。
Bさんは2016年2月に入社して以降、順調に職場へ適応し長期勤務を続けており、上司も「彼がいてくれるだけで社内が明るくなる」とその存在価値を評価しています。
この事例からは、大企業においても支援機関と協働し慎重にマッチングを図ることや、受け入れ側社員の意識変化が定着成功のカギとなることが伺えます。
積水化学工業株式会社
京都に本社を構える大手化学メーカーの積水化学工業株式会社では、早くから発達障がい者の雇用に取り組み、社内で「個人の持ち味を活かし組織とともに成長を」というスローガンを掲げています。
積水化学では障がい者一人ひとりの強みに着目し、それを活かせる業務を切り出して任せています。
例えば、あるADHDの社員は細かい数値チェック作業は苦手な一方、単純作業を根気強く続けることに長けていたため、製品の検品ラインに配置したところ力を発揮し、作業効率向上に貢献しました。
さらに、定期面談で将来の希望を聞き、希望に応じて新たな仕事にチャレンジできる場を与えるなど、社内異動のチャンスも提供しています。
その結果、障がい者社員のモチベーションが高く維持され、多くの社員が5年以上勤続し中には10年以上キャリアを積んでいる方もいます。
積水化学のように大企業の場合、部署数も多く様々な職種が存在するため、本人の適性にフィットするポジションを社内で見つけやすいという利点も長期就労に寄与していると言えます。
中小企業の事例:関西の中小企業での定着への工夫
関西には中小企業においても、障がい者雇用の定着が優れている事例があります。
株式会社福原精機製作所(中小製造業)
兵庫県姫路市の株式会社福原精機製作所(中小製造業)では、知的障がい者・発達障がい者の雇用に早くから取り組み、社内の整理整頓・清掃業務や軽作業の分野で力を発揮してもらっています(※兵庫県雇用開発協会「障害者雇用好事例集」より)。
同社では、障がい者社員に対してマンツーマンの指導担当を付け、新人期間は毎日終業後に振り返り面談を行いました。
現場作業では作業手順を写真入りマニュアルにして壁に貼るなど、誰でもわかる仕組みを整えました。
その結果、障がい者社員は安心して業務を覚えることができ、5年以上の勤続を遂げています。
代表者は「多少時間はかかっても、一度覚えた仕事は丁寧に確実にこなしてくれる」と評価しており、健常者社員にも良い刺激になっていると述べています。
株式会社エムツープレスト(小規模製造業)
大阪府摂津市の株式会社エムツープレスト(小規模製造業)は、発達障がい者の雇用で成果を上げた企業として知られています。
同社社長は「障がいのある方もいて当然。会社は世の中の縮図に近い自然な場であるべき」との考えで、特別扱いをしない包容力ある社風を作りました。
発達障がいのある社員には、製品の3S(整理・整頓・清掃)活動を任せていますが、几帳面さやこだわりの強さが発揮され、工場の整備状況が飛躍的に改善されたそうです。
社長は「彼らの“足りなさ”や“難しさ”こそ成長の鍵」と語り、難しい作業も少しずつ段階を追って教えることで、本人ができることを増やし自信に繋げています。
こうした取組により、エムツープレストでは障がい者社員の離職はほとんどなく、健常者社員からも「障がいのある同僚から学ぶことが多い」という声が上がっています。
中小企業の場合、大企業のように豊富な配置転換先や専門スタッフがいない分、職場全員で助け合う家族的な雰囲気が強みとなります。
それを上手く活かし、一人ひとりに目を配りケアできている中小企業ほど、平均勤続年数が長い傾向が見られます。
特例子会社や支援機関との連携による定着支援
関西地域では、障がい者雇用の特例子会社やNPO法人など支援機関が活発であり、そうした専門組織と連携する企業も平均勤続年数の向上に成功しています。
パーソルグループの特例子会社であるパーソルダイバース株式会社(大阪にも拠点あり)では、社内に約1,000名以上の精神・発達障がいのある社員が在籍し、ジョブコーチや産業医、カウンセラーが連携した総合支援体制で社員の長期活躍を実現しています。
同社の事例では、精神障がいのある社員の長期就業をテーマに、当事者に工夫していることをヒアリングしたところ、「紙に気持ちを書き出して整理する」「ネガティブな言葉をポジティブに言い換える」など自己安定の工夫が紹介されました。
これらは個人の取り組みですが、会社側がそのような自己理解・自己成長の機会を提供し促している点に注目できます。
特例子会社や大企業だけでなく、関西のNPO法人大阪障害者雇用支援ネットワーク(ESネット)なども企業向けに発達障がい者雇用促進セミナーや定着支援研修を行っており、地域ぐるみで定着率向上に努める動きがあります。
中でもNPO法人JSN(大阪市)は、就労移行支援で訓練を経て就職した障がい者の職場定着率(就職1年目)が98%に達したとの報告もあり[57]、専門的な支援プログラムの効果が伺えます。
企業単独で難しい部分は、このように外部の力を借りることも長期定着には有効。
関西圏はこうした支援リソースが豊富であるため、積極的に活用する企業ほど結果的に平均勤続年数が伸びる傾向にあります。
関西における行政のサポートと企業の取り組み動向
大阪府では「大阪府ITステーション就労促進事業」など、ITスキル習得を通じた障がい者の就労支援拠点を設置し、企業と障がい者のマッチングを支援しています。
また、「精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業」として、企業向けの理解促進セミナーや職場定着に向けた助言を専門家が行う事業も実施されています。
これら行政のバックアップもあり、関西では製造業からサービス業まで幅広い業種で障がい者雇用の好事例が生まれています。
総じて関西の企業は、「人」を大事にする社風が根付いているところが多く、障がい者もチームの一員として迎え入れ長く活躍してもらおうという意識が強いようです。
「5年後も10年後も一緒に成長できる関係を」と掲げる大阪のベンチャー企業もあるように、短期的な雇用数の達成だけでなく将来を見据えた人材育成の視点で障がい者雇用に取り組む企業が増えている点が、関西における特徴と言えるでしょう。
株式会社アルファ・ネットコンサルティング:アクセル
株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。
「法定雇用率を満たせない」
「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、
障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、
ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。
サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。
-300x118.jpg)