発達障害の一つであるADHD(注意欠如・多動症)を含む障がいのある方の雇用を検討している企業経営者の皆様に向けて、活用できる助成金や支援制度を網羅的にご紹介。
障がい者雇用には初期導入や職場環境整備にコストや手間がかかることがありますが、公的な助成金や支援策を活用することで負担を軽減し、戦力となる人材の活躍を後押しできます。
本記事では全国共通で利用できる主な助成金制度を目的別に整理し、特に大阪府における独自の支援策については詳しく解説。
ADHDの方も対象となる制度が多く、貴社の障がい者雇用促進に役立つ情報をまとめました。
国の障がい者雇用助成金(採用時に活用できるもの)
まず、障がい者の採用段階で利用できる代表的な国の助成金を紹介します。
新たに障がいのある方(ADHDを含む)を雇い入れる企業に対して支給されるもので、主にハローワーク等を通じた採用が条件です。
大きく「特定求職者雇用開発助成金」と「トライアル雇用助成金」の2種類があります。
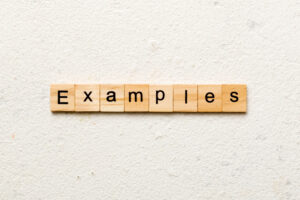
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、就職が特に困難とされる求職者を継続雇用した事業主に支給される国の助成金制度です。
高年齢者や障がい者の方などが対象で、ハローワークや民間の人材紹介会社の紹介により雇用した場合に申請できます。
コースが2つに分かれており、それぞれ支給額や条件が異なります。
●特定就職困難者コース
身体・知的・精神障害者の方などが対象。支給額は一人当たり 80万円~240万円 と幅があり、企業規模(中小企業か否か)や障害の程度、雇用形態(週30時間以上のフルタイムか否か)によって変動します。
中小企業ほど高額になり、重度障害者やフルタイム雇用の場合に上限額に近づきます。
●発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害(ADHD等)や難病のある方が対象。
支給額は一人当たり 30万円~120万円 と設定されており、こちらも企業規模や労働時間、障害の程度によって増減します。
例えばADHDなど発達障害のある方を中小企業がフルタイムで雇用した場合は上限に近い額が支給されます。
適用条件
いずれのコースも、雇用する求職者がハローワークまたは厚生労働省許可の民間職業紹介事業者の紹介であること、雇用保険の被保険者として継続雇用すること(契約期間の定めがないか6か月以上など)が共通の条件です。
またコースごとに対象となる障がい種別が定められており、ADHDの場合は「発達障害者コース」の対象となります。
申請方法と支給形態
管轄の労働局またはハローワークに必要書類を提出して申請します。
助成金は一括ではなく一定の雇用期間ごと(支給対象期ごと)に分割支給される点に注意が必要です。
6か月ごとに支給申請を行い、支給額を受け取る形式となります。
申請期限も各支給対象期間の終了後2か月以内と決まっているため計画的な手続きが求められます。
障害者トライアル雇用助成金
障害者トライアル雇用助成金は、障がいのある方を一定期間試行雇用(トライアル雇用)した事業主に支給される助成金です。
いきなり本採用とするのではなく、まずはお試し雇用で企業と本人の相性や適性を確認しあう制度で、ミスマッチの防止や雇用機会の創出を目的としています。
特に職務経験が少ない方や、離職・転職を繰り返している方への就労機会提供に有効です。
トライアル雇用助成金には「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2種類があります。
支給額と対象者が異なるため、それぞれ解説します。
●障害者トライアルコース
原則として週20時間以上の勤務が可能な障がい者の方を試行雇用する場合のコースです。支給額は、精神障害者を雇用した場合に特例があり、最初の3ヶ月は月額最大8万円、その後の3ヶ月は月額最大4万円(最長6ヶ月間)支給されます。
ADHDのように精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方であればこの特例対象となり、6ヶ月間で最大36万円(8万×3 + 4万×3)の助成を受けられます。
それ以外の障害種別の方については月額最大4万円を3ヶ月間(最長3ヶ月まで)受給可能です。
●障害者短時間トライアルコース
ADHDを含む発達障害や精神障害のある方で「いきなり週20時間以上働くのが難しい」ケースに対応したコースです。
週10時間程度からの短時間勤務で試行雇用を開始し、徐々に働く時間を延ばしていくことを目的としています。
支給額は月額最大4万円を最長12ヶ月間受給できる仕組みで、1年近く支援を受けながら段階的に本格雇用へ移行することが可能です。
適用条件
障害者トライアルコースを利用するには、対象となる求職者が以下のいずれかに該当する必要があります
・就労経験のない職種への就職を希望している
・過去2年以内に離職や転職を2回以上繰り返している
・直近の離職期間が6ヶ月を超えている
・重度身体障害、重度知的障害、または精神障害者である
上記に該当し、かつトライアル雇用を希望している障がい者の方が対象です。
企業側の条件としては、ハローワーク等の紹介で雇い入れること、トライアル雇用期間中は雇用保険に加入させること(短時間コースの場合は除く)などがあります。
短時間トライアルコースは特に「精神または発達障害者」で短時間勤務から開始することを希望する方のみ対象となります。
申請方法
トライアル雇用助成金の申請もハローワークが窓口。
必要書類を準備のうえ、所轄のハローワークに提出して申請します。
提出期限はコースによって異なり、本コース(障害者トライアルコース)はトライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内、短時間コースは短時間トライアル開始日から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内と定められています。
期限を過ぎると支給されませんので注意が必要です。
国の障がい者雇用助成金(雇用継続・職場環境整備に関するもの)
次に、雇い入れた障がい者の方が長く安定して働けるように支援する目的で設けられている助成金を紹介します。
職場環境の改善やスキルアップ支援、雇用形態の転換など、定着促進につながる取組みに対して支給されるものです。
代表的な制度として「障害者雇用安定助成金」「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」「障害者能力開発助成金(旧人材開発支援助成金)」および「在宅就業障害者特例調整金」があります。
障害者雇用安定助成金
障害者雇用安定助成金は、障がい者の方が働き続けやすい職場づくりのために企業が行う各種取組みに対して支給される助成金です。
具体的には職場環境の整備(設備の改善や作業施設の設置改良など)や、専門スタッフによる職場適応支援(ジョブコーチの配置等)を実施した場合に助成されます。
障がい者の職場定着を図ることが目的であり、職場内の障壁除去や人的支援に要した費用の一部を補助してくれる制度。
障害者雇用安定助成金にはいくつかコースがありますが、中小企業に関係が深い主なものは次の二つです。
●障害者職場適応援助コース
障がい者の職場適応を専門にサポートする担当者(職場適応援助者、いわゆるジョブコーチ)を配置または外部から招いて支援を行った場合に助成されるコースです。
自社社員をジョブコーチとして養成・配置する「企業在籍型」か、外部の支援機関からジョブコーチに来てもらう「訪問型」かで助成額が異なります。目安として、企業在籍型の場合は1人当たり月額4万~12万円が支給されます(企業規模や障害種別により幅あり)。訪問型の場合も支援実施にかかった費用の一部が助成されます。例えば障がい者の方1名に対し3ヶ月間ジョブコーチを付けた場合、該当期間のジョブコーチ人件費等に対して所定額が支給されます。
●中小企業障害者多数雇用施設設置等コース
複数の障がい者を雇用している中小企業が、職場の作業環境や福利厚生施設を整備・改善する際に利用できるコースです。
例えば、車椅子利用者のために社屋をバリアフリー改修したり、休憩室や更衣室を障がい者が使いやすいよう改造した場合の費用が助成対象となります。支給額は1件あたり250万円~1,500万円と高額で、実際にかかった設備設置費用に応じて助成されます。
助成率や上限額は設備内容によりますが、中小企業が多数の障がい者を受け入れるための環境整備を強力に後押ししてくれる制度です。
※上記の他、「障害者介助等助成金」や「中高年障害者の職場適応助成金」など細分化されたメニューもあります。
重度障がい者の方に職場介助者(付き添い支援者)を付ける措置を講じた場合の助成や、障がい者の通勤を容易にするための送迎サービス提供に対する助成など、企業の具体的なニーズに応じた支援策が用意されています。
これらは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に事業が移管されており、該当する取り組みを行った際に別途申請することで費用補助を受けることが可能です。
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
キャリアアップ助成金は、有期雇用契約の労働者を正社員化するなど雇用形態の転換を行った企業に支給される助成金です。
障がい者の方の雇用促進と職場定着を目的に設けられたコースがあり、障がい者をより安定した立場で雇用する取り組み(非正規から正社員化等)に対して助成されます。
●支給額
障害者正社員化コースで受給できる額は 33万円~120万円 程度で、企業の規模(中小か大企業か)、転換前後の雇用形態、障がいの程度などによって細かく定められています。
最大額の120万円が支給されるケースの一例として、中小企業が精神障害者(例:ADHDなどで精神障害者保健福祉手帳を所持)の社員を有期契約から正規雇用へ転換した場合が挙げられます。
逆に支給額が低くなるのは、障害の程度が軽い方を無期雇用から正規雇用に転換した場合などです。
いずれにせよ、中小企業の方が助成額は高めに設定されています。
●適用条件
支給を受けるには事前に「キャリアアップ計画」を策定し、所轄の労働局長の認定を受けておく必要があります。
その上で、計画に沿って例えば「有期契約社員を無期雇用社員に転換」し、転換後6ヶ月間継続勤務させた段階で申請を行います。
転換後6ヶ月分の給与を支給した翌日から2ヶ月以内に必要書類を提出する流れです。
計画認定を事前に受けていないと助成対象になりませんので、制度活用を検討する際は早めに労働局等に相談すると良いでしょう。
障害者能力開発助成金(旧人材開発支援助成金)
障害者能力開発助成金は、障がい者の職業上の能力を高めるための教育訓練施設の設置・運営に対して支給される助成金です。
2024年4月に新設された制度で、それ以前は「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」として実施されていたものが移管・拡充されました。
この助成金は、企業または事業主団体が障がい者に必要な職業訓練を継続的に提供するための施設を自社で設置・運営した場合に受け取ることができます。
例えば、社内に障がい者向けの研修センターやトレーニングルームを開設し、ADHDなど発達障害のある社員に対して業務スキル向上の研修を定期的に実施するといったケースが該当します。
●支給内容
助成率は高く、施設の新規設置にかかった費用の3/4が助成されます(初回の施設設置なら上限5,000万円まで)。
既存施設の改修・更新の場合は上限1,000万円までです。
さらに、施設を運営する際の経費についても支援があり、運営費の4/5(中小企業の場合)または3/4(中小企業以外の場合)が助成。
運営費助成にも上限額が設けられますが、人件費や教材費等の大部分をカバーできる非常に手厚い内容です。
●適用条件と申請
障害者能力開発訓練施設を設置・整備する際は、着工前に管轄労働局長の認定を受ける必要があります。
認定後、施設の設置が完了した日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行います。
運営費については、訓練開始の3ヶ月前までに計画認定を受けた上で、一定の期間ごと(支給対象期間の末日翌日から2ヶ月以内)に申請します。
要件が専門的でハードルは高い制度ですが、例えば特例子会社や大企業が社内訓練センターを設立するケースだけでなく、中小企業がグループで合同訓練施設を運営する場合などでも活用が検討できます。
検討中の企業様は労働局等へ事前相談されると良いでしょう。
在宅就業障害者特例調整金
在宅就業障害者特例調整金は、障がい者の方が自宅等で就業(在宅就労)できる機会を増やすため、在宅で働く障がい者や支援団体に業務を発注した企業に支給される助成金です。
例えば、フリーランスで在宅就業している発達障害者の方に仕事を委託し報酬を支払った場合や、在宅就労支援団体(在宅ワークを斡旋するNPO等)に業務委託した場合に、企業に対して奨励金が支給されます。
●支給額
支給額は委託した業務の対価額に比例して算出されます。
具体的には「年間支払報酬総額の約6%相当」が目安です。
1年間に在宅の障がい者へ業務委託で210万円の報酬支払いを行った企業の場合、約12万6千円(210万円の6%)が支給される計算になります。
この6%という比率は「評価額35万円につき調整額2万1千円」の計算式に基づくもので、中小企業・大企業問わず適用されます。
一方、常用労働者数が100人以下の中小企業については別枠の報奨金(定額1万7千円)が用意されており、在宅障がい者への発注実績に応じて支給されます。
●特徴
この特例調整金は、直接雇用ではなく業務委託という形で障がい者の就業機会を創出した場合に企業を奨励する珍しい制度です。
在宅で働くことを希望する障がい者の方は近年増えており、企業としてもテレワーク等で外部人材に業務委託するケースが増えています。
そうした取り組みが間接的に障がい者雇用促進につながる場合、一定の経済的メリットを受けられる仕組みになっています。
なお、本助成金の申請や支給決定は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(各都道府県の支部)で行われ、毎年4月から申請受付期間が設定されています。
詳しい算定方法や申請スケジュールについては支援機構の窓口で確認することをお勧めします。
その他の国の障がい者雇用支援制度
上記の助成金のほかにも、企業の障がい者雇用を後押しする支援制度が国や関係機関から提供されています。
ここでは金銭的助成以外も含め、知っておきたい主な支援策をまとめます。
障害者雇用納付金制度(調整金・報奨金)
障害者の法定雇用率制度に関連して、「障害者雇用納付金制度」があります。
一定規模以上の企業は法定雇用率を下回ると不足1人当たり月5万円の納付金を徴収されますが、一方で法定雇用率を上回って障がい者を雇用している企業には奨励金が支払われる仕組みになっています。
障害者雇用調整金超過雇用している障がい者1人あたり月額29,000円(※2024年度以降の上限額)が支給されます。
ただし、大幅に超過する場合、一定人数を超えた部分については1人当たり23,000円に減額調整されます。
障害者雇用報奨金
中小企業など常用労働者100人以下で法定雇用率を達成している事業主に対し、超過雇用している障がい者1人当たり月額21,000円の報奨金が支給されます。
中小企業の場合、そもそも法定雇用義務が生じない規模でも障がい者を雇用すればこの報奨金の対象となり得ます。
例えば従業員30名規模の会社で1名の障がい者を雇用しているケースでは、法定雇用率上は0名義務のところ1名雇用しているため、その1名分について報奨金(月21,000円)が受け取れる計算です。
これら調整金・報奨金は企業が申請手続きを行う必要があります(毎年、前年度の実雇用状況に基づき申告)。障害者の雇用状況報告と合わせて各企業が申請することで、厚生労働省所管の独立行政法人(JEED)から交付されます。
法定雇用率未達成の場合の納付金とセットで運用される制度ですので、自社がどちらに該当するか毎年度確認しておきましょう。
ジョブコーチによる職場定着支援
障がい者の方を受け入れる際、「ジョブコーチ」(職場適応援助者)による支援制度も活用できます。
ジョブコーチとは、障がい者の職場への適応を専門的にサポートする担当者のことで、国の委託事業として各地域の障害者職業センター等から派遣を受けることができます。
ジョブコーチは企業と障がい者双方の立場に立って、職務の教示方法やコミュニケーション面の調整など実践的な支援を行い、職場定着を促します。
●利用方法
公共職業安定所(ハローワーク)や地域障害者職業センターに相談すると、必要に応じてジョブコーチの派遣を受けられます。
費用は国が負担するため企業の自己負担はありません。
支援期間は数ヶ月程度で、ジョブコーチが定期的に職場を訪問し支援・助言を行います。ジョブコーチによる支援を実施した企業は、前述の障害者雇用安定助成金の「職場適応援助コース」の対象ともなり、社内に配置する場合の助成金を受け取ることもできます。
ADHDを含む発達障害のある方は、職場でのコミュニケーションのズレや環境変化への戸惑いが起きやすい場合がありますが、ジョブコーチのきめ細かなフォローによって早期戦力化・定着が期待できるでしょう。
初めて障がい者を雇用する企業様は、ジョブコーチ支援を積極的に活用すると安心です。
障害者雇用相談援助事業(新設コンサルティング支援)
2024年度からスタートした新たな支援策に「障害者雇用相談援助助成金」があります。
これは、厚生労働省が認定した民間事業者(社会保険労務士法人等)が、中小企業に対して障がい者雇用に関する相談援助サービスを提供した場合に、その事業者に対して助成金を支給する制度です。
簡単に言えば障がい者雇用の専門コンサルティングを企業が無料で受けられる仕組みといえます。
具体的には、認定事業者が企業からの相談に応じて、障がい者の新規雇用計画の策定支援や職場環境整備のアドバイス、定着支援プログラムの実施など包括的なサポートを提供します。
その結果、支援を受けた企業が実際に障がい者の雇入れや雇用継続の措置を講じた場合に、事業者側に1件あたり60~80万円の助成金が支給されます。
企業にとっては直接お金をもらえる制度ではありませんが、専門家の支援サービスを実質無料で受けられるメリットがあります。
厚生労働省はこの制度により、特にノウハウの乏しい中小企業への丁寧な支援を強化しています。
大阪労働局でも令和6年4月より相談援助事業者の認定・周知を開始していますので、障がい者雇用を検討中で専門的な助言がほしい企業様は、労働局やハローワークに問い合わせてみるとよいでしょう。
ハローワーク等による各種支援サービス
このほか、ハローワーク(公共職業安定所)や地域の障害者職業センターでも企業向けの支援メニューが提供されています。
ハローワークには「障害者専門援助部門」があり、障がい者の職業紹介はもちろん、企業からの求人相談・人材マッチングの支援を行っています。
面接時に配慮が必要な場合の助言や、トライアル雇用の利用手続き支援なども。
また、ハローワーク経由で職場実習(トライアル雇用の事前体験的なもの)を受け入れることも可能です。
一定期間(例えば2週間など)、候補者が職場体験を行い、双方合意の上で正式雇用につなげる制度で、受入企業には実習中の損害保険等のサポートがあります。
実習自体に賃金は発生しませんが、求職者側には職業訓練給付が支払われるため企業負担なく実習の機会を提供できます。
ADHDの方の場合、実際の職場環境で適性を見極めるのに有効な手段となります。
地域障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県センター)では、各種専門家による相談支援が受けられます。
職場復帰支援やメンタルヘルス面の相談、合理的配慮の具体策に関する助言など、無料で利用できます。
必要に応じて先述のジョブコーチ派遣調整も行われます。
企業単独では解決しにくい課題も、公的機関のネットワークを活用すれば解決策が見つかる場合がありますので、積極的に活用しましょう。
大阪府における障がい者雇用支援制度
全国共通の制度に加えて、大阪府独自の取り組みや、府内自治体による支援制度もあります。
大阪府は条例や独自施策を通じて中小企業の障がい者雇用促進を後押ししており、国の制度と組み合わせて利用することで一層のメリットが得られます。
ここでは大阪府内で活用できる主な支援策をご紹介します。
大阪府ハートフル税制(独自の税優遇措置)
大阪府では、「大阪府障がい者の雇用の促進及び職業の安定に係る法人事業税の特例」に基づき、一定の要件を満たす法人に対して府税の軽減措置を講じるハートフル税制を実施しています。
これは法人事業税(地方税)の負担を軽減するもので、法定雇用率を上回る障がい者雇用を行っている企業が対象です。
ハートフル税制にはいくつか区分がありますが、中小企業に適用される代表的区分として「障がい者多数雇用中小法人」があります。
要件の概要は次のとおりです。
●常時雇用する労働者数が100人以下の中小法人であること。
●府内事業所における平均雇用障がい者数が、企業規模に応じて定められた基準を超えていること(例:従業員40人未満なら2人超、40~80人未満なら3人超、80~100人なら4人超)。
上記を満たす法人は、該当事業年度の法人事業税率が10%軽減(現行税率の90%に減免)されます。
ただし税額軽減には上限があり、納める税額が一定以上減る場合はその額で頭打ちとなります。
また同一年度に他の特例(大阪成長特区税制など)との重複適用はできません。
例えば従業員50名の大阪府内企業で障がい者を4名雇用している場合、法定雇用率2.5%に対して実雇用率8%と大きく上回っています。
この企業がハートフル税制の適用を申請すれば、要件を満たせば法人事業税の税率が1割引きになり、納税額が軽減。
税制優遇は資金繰りに直接プラスとなるメリットですので、府内企業で一定数の障がい者を雇用している場合は是非活用したい制度です。
適用には事業年度終了後に大阪府税事務所への申告が必要ですので、詳しくは大阪府の案内ページをご確認ください。
専門家派遣・相談支援(大阪府障がい者雇用専門家派遣制度 等)
大阪府は障がい者雇用に取り組む企業への技術的支援として、「障がい者雇用専門家派遣制度」を実施しています。
障がい者の受け入れや職場定着について課題を抱える事業主のもとへ、府の障がい者雇用促進センターに登録された専門家(コンサルタント)を派遣し、問題解決を支援する制度です。
●支援内容
専門家は企業とのヒアリングを行い、課題に応じた助言や職場改善の提案を行ってくれます。
例えば「ADHDの社員のミスが多く困っている」「障がい者にどのような業務を任せればよいかわからない」といった相談に対し、業務切り出し(ジョブカービング)の方法や効果的な指導計画の策定、周囲社員への理解促進策など具体的なアドバイスを受けることができます。
相談例として、大阪府の資料では「障がい特性に合わせた業務マニュアルの作成方法」「職場内コミュニケーション改善」等が挙げられています。
●費用
大阪府の専門家派遣は基本的に無料で利用できます(府の予算事業として行われるため)。派遣日程や回数は企業の状況に応じて調整され、1社あたり数回程度の訪問支援が行われます。
専門家は社会保険労務士や産業カウンセラー、障害者職業カウンセラーなど経験豊富な人材が担当しますので、実践的なノウハウが得られるでしょう。
この他にも、大阪府ではIT分野に特化した支援拠点「大阪府ITステーション」を設置しています。
ITステーションではIT関連業務で障がい者の雇用を検討している企業に対し、専門のコーディネーターが無料で相談に乗ったり、企業向けセミナーを開催したりしています。
ADHDの方はIT・クリエイティブ分野で才能を発揮するケースも多く、そうした人材の雇用を検討する企業には心強いサポートになるでしょう。
大阪府障がい者サポートカンパニー登録制度
大阪府は、障がい者の雇用や職場実習の受入れに積極的に取り組む企業を「大阪府障がい者サポートカンパニー」として登録・認証する制度を設けています。
これは直接的な助成金ではありませんが、企業の社会的評価を高める支援策として注目できます。
●制度概要
一定の要件(障がい者雇用の実績や実習受入れ実績等)を満たした企業・団体は、大阪府福祉部に申請し審査を経てサポートカンパニーとして登録されます。
登録企業には大阪府より認証書が交付され、府のホームページで企業名が公表されるなどPR支援が行われます。
また、登録企業は自社のパンフレットや名刺等に大阪府就労支援ロゴマークを使用することが許可され、対外的に障がい者雇用に熱心な企業であることをアピールできます。
●メリット
登録自体に金銭的メリットはありませんが、人材採用面で企業イメージ向上につながるほか、登録企業間の情報交換ネットワークに参加できる利点があります。
大阪府主催の交流会やセミナーに招待され、障がい者雇用の先進事例を学べる機会も提供されます。
中小企業にとっては行政のお墨付きが得られることで取引先や顧客からの信頼が高まる効果も期待できます。
ADHDを含む発達障害者の雇用に前向きに取り組んでいる企業様は、ぜひサポートカンパニー登録を目指してみてはいかがでしょうか。
登録要件等の詳細は大阪府の担当部署(就業促進課障がい者雇用促進グループ)に問い合わせることができます。
大阪府障がい者雇用促進センターの活用
大阪府は独自の「障がい者雇用促進センター」を運営しており、府内企業と障がい者求職者のマッチング支援を行っています。
同センターには職業訓練施設で専門訓練を受けた障がい者の方(職業訓練生・修了生)の人材バンクがあり、企業の求人ニーズに合った人材を紹介してもらえます。
ハローワークとは別に大阪府独自の人材紹介ルートがあるイメージで、特に府立の障がい者職業能力開発校等を卒業した方の就職支援に強みがあります。
例えば、大阪障害者職業能力開発校でITスキルを習得した発達障害のある方を、自社のIT部門に紹介してもらうといったことも可能です。
利用方法は、企業が障がい者雇用促進センターに求人登録を行い、センターの職業紹介担当者との打ち合わせを経てマッチングを図ります。
必要に応じて見学や実習の調整などもサポートしてもらえます。
大阪府内で障がい者の人材を探している企業は、このような地域のリソースも活用すると良いでしょう。
大阪府内市町村による奨励金制度の例
大阪府内の一部自治体では、国の助成金に加えて独自の雇用奨励金を設けている場合があります。
大阪府茨木市や高槻市では「障害者雇用奨励金制度」を実施しており、対象となる障がい者を雇用した事業主に対して奨励金を支給しています。

茨木市の例
茨木市では、市内在住の重度身体・知的・精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇用し、さらに国の特定求職者雇用開発助成金を受給した事業主に対し、追加の奨励金を支給しています。
支給対象期間は国の助成金支給終了後から一定期間となっており、支給額は雇用した障がい者1人あたり年間数十万円程度が複数年にわたって支給される仕組みです(雇用形態等により異なる)。
高槻市の例
高槻市でも、高槻市在住の障がい者を新たに雇用した事業主に奨励金を支給しています。令和6年の制度改正により要件緩和・拡充が図られており、支給額は雇用した障がい者1人につき一時金で数十万円が支給されます。
特に市内在住者の就労機会創出を目的としているため、地域貢献にもつながる制度です。
まとめ:組み合わせて最大限活用
国の助成金同士、あるいは国と自治体の制度を組み合わせて活用することで、経済的支援を最大化できます。
例えば「特定求職者雇用開発助成金」で初期の雇用コスト支援を受けつつ、「障害者雇用安定助成金」で職場定着のサポート、「ハートフル税制」で税負担軽減、といった具合に多面的なメリットを享受できます。
ただし重複適用が制限される場合もあるため、事前に確認しましょう。
株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。
「法定雇用率を満たせない」
「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、
障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、
ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。
サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。




