社員の中に「注意力が散漫でミスが多い」「落ち着きがなく衝動的」な人がいて、その対応に悩んだ経験はありませんか?
こうした特徴を持つ可能性があるのがADHD(注意欠如・多動症)です。
本記事では、大人のADHDの基本的な特徴と診断基準を詳しく解説し、脳の働きなど背景にある要因を簡単にご紹介。
さらに、職場でADHDのある人が人間関係でつまずきがちなポイントやコミュニケーションのコツ、対人トラブルを防ぐ方法について、マネジメント視点も交えながら具体的に取り上げます。
最後に、中小企業が障がい者雇用としてADHD人材を受け入れる際に配慮すべき点や活用できる支援制度、参考になる事例もご紹介します。
ADHDへの正しい理解と適切なサポートによって、多様な人材が活躍できる職場づくりのヒントになれば幸いです。
ADHDとは?成人の特徴と診断基準
ADHD(注意欠如・多動症)は、子どもだけでなく成人にも見られる発達障がいの一つです。
大人になってからも不注意や衝動性が続くことで、仕事や人間関係に影響が出ることがあります。
ここでは、ADHDの医学的な定義や診断基準、成人特有の症状、脳の働きとの関係についてわかりやすく解説します。
職場での誤解を防ぎ、正しく理解するための基礎知識を身につけましょう。

ADHD(注意欠如・多動症)の基本概要
ADHDは「注意欠如・多動症(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)」と呼ばれる発達障がいの一種です。
生まれつき脳の注意や行動をコントロールする機能に偏りがあるために、次のような特性が現れます。
●不注意
集中力を持続することが苦手ですぐに気が散ってしまう、ケアレスミスが多い、物事を順序立てて行うのが苦手など。
●多動性
落ち着きがなくそわそわと体を動かしてしまう、静かにじっとしていられない、必要以上にしゃべり続けてしまう等。
●衝動性
思いついたら考えるより先に行動してしまう、順番を待つことが極端に苦手、会議中につい人の話を遮って発言してしまう等。
これらの特性の現れ方には個人差があり、「不注意優勢型」「多動性・衝動性優勢型」および両方の特性を併せ持つ「混合型」に分類されます。
発達障がいの中でも頻度が高い障がいであり、かつては子どもに多いと考えられていましたが、成人の約3~5%にADHDがみられるとの報告もあり(WHOの推定では世界的な成人ADHD有病率3.4%)、大人になっても症状が続くケースが少なくありません。
男女比はおおむね2対1で男性に多いことが知られています。
ADHDのある人は学習障害(LD)やチック症、うつ病・不安障害などを併存することも多く、生活上の困難から二次的に精神的な不調をきたす場合もあります。
単なる性格の問題ではなく、生来的な脳機能の特性による「発達障がい」である点をまず押さえておきましょう。
成人におけるADHDの診断基準と具体的な症状例
ADHDかどうかは専門の医師がDSM-5という国際的な診断基準に照らして判断します。診断基準では不注意症状と多動・衝動症状の2グループにそれぞれ9つの具体的項目があり、そのいずれかで一定数以上該当すればADHDと診断されます。
例えば主な項目には次のようなものがあります。
ADHDかどうかは専門の医師がDSM-5という国際的な診断基準に照らして判断します。診断基準では不注意症状と多動・衝動症状の2グループにそれぞれ9つの具体的項目があり、そのいずれかで一定数以上該当すればADHDと診断されます。
例えば主な項目には次のようなものがあります。
【不注意の症状例】
●細かいところまで注意が行き届かず、しばしばケアレスミスをしてしまう。
●課題や作業に最後まで集中を維持することが難しい。
●人の話を聞いていないように見えることがある。
●指示に従えず仕事や用事をやり遂げられない。
●物事を整理したり段取りを組むのが苦手。
●必要なものをよくなくす、忘れ物が多い。
●外部からの刺激ですぐ注意がそれてしまう。
【多動性・衝動性の症状例】
●座っていても手足を貧乏ゆすりするなど落ち着かない。
●会議中など状況にそぐわず席を立ってしまう。
●静かにしていようとしてもついおしゃべりが過ぎてしまう。
●質問が終わる前に考えず答えを口走ってしまう。
●順番を待てず列に割り込んでしまう。
●他の人の会話や作業に不意に割り込んで邪魔をしてしまう。
上記のような状態が幼少期(12歳以前)から見られ、家庭や職場など複数の環境で機能障害を起こしていることが診断には必要です。
なおDSM-5から診断基準が拡張され、17歳以上の成人では各症状グループで5つ以上該当すれば診断可能と緩和されました(小児は6つ以上)。つまり大人になってから顕在化したように見える場合でも、振り返れば子どもの頃から不注意・多動傾向があったはずだと考えられます。
ただし大人は子どもより環境や役割が多様なため、症状の現れ方も人によってさまざまです。
そのため本人や周囲がADHDだと気づかずに過ごし、「大人になって初めてADHDと診断される」ケースも決して珍しくありません。
ADHDの脳機能的な背景(なぜ起こる?)
ADHDは医学的には「神経発達症」に分類され、先天的な脳機能の偏りが関係するとされています。
原因は完全には解明されていませんが、遺伝的な要因や出生前後の環境要因などが複雑に影響し、脳内の神経伝達の機能不全を引き起こすと考えられます。
具体的には、前頭前野(注意や実行機能を司る脳の部位)の働きを調節するドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の活動が低下していることが分かっています。
これにより、物事に優先順位をつけて計画・実行する「実行機能」が弱まり、衝動を抑えて我慢することや、意欲・快感をコントロールする「報酬系」の働きにも障害が現れると考えられます。
簡単に言えば、脳のブレーキ役や切り替え役がうまく機能しづらい状態なのです。
このため、本人の努力や意志だけでは克服が難しい面があり、周囲の理解と環境調整が極めて重要になります。
「親のしつけの問題」「本人の性格や怠け」などが原因ではないことを強調しておきます。むしろ医学的にはれっきとした脳の特性による障がいであり、適切な治療(薬物療法や認知行動療法など)やサポートによって症状の改善が期待できるものです。
大人のADHDならではの特徴と日常生活への影響
ADHDの主症状は成長とともに変化することがあります。
多動性については子どもの頃ほど目立たなくなるケースが多く、成人では椅子に座ってじっとしていられないような極端な多動は減じる傾向があります。
しかし不注意や衝動性は成人期でも中心的な症状として残りやすく、生活の中で様々な困難を引き起こします。
例えば、社会人になってからは以下のような影響がよく見られます。
●仕事のミスや納期遅れ
注意散漫さや段取りの悪さから、業務でケアレスミスを繰り返したり、仕事を最後までやり遂げられないことがある。
この結果、評価に響いたり自己効力感の低下につながる場合があります。
●対人面のトラブル
思ったことをすぐ口に出してしまう衝動性や、感情のコントロールの難しさから、上司・同僚と言い争いになったり、人間関係がぎくしゃくすることがあります。
誤解から孤立感を深めるケースもあります。
●日常生活でのミス
約束を忘れる、請求書の支払いを失念する、部屋の片づけや時間管理がうまくできず生活が混乱しやすい、といった問題が生じがちです。
これが慢性的な自己否定感やストレス要因となることもあります。
●二次的な精神的不調
こうした失敗体験の積み重ねや周囲からの叱責により、自己評価が下がりうつ病や不安障害を併発するケースもあります。
また注意力の不足から交通事故や労災事故に遭うリスクも高いことが報告されています。
一方で、ADHDの症状は環境や工夫次第で軽減することも知られています。
子どもの頃は成長とともに50~60%のケースで症状が改善するとされ、成人まで持続するのは約半数と報告されています。
大人になっても症状が残る場合でも、本人が自分の特性を理解して対処法を身につけたり、得意な分野で能力を発揮することで、弱みを補いながら社会生活を営んでいる人もたくさんいます。
また最近では大人のADHDに対する治療薬や心理療法の選択肢も広がっており、症状コントロールもしやすくなっています。
つまりADHDは克服というより「付き合い方を学ぶ」べき特性であり、周囲の適切なサポートがあれば十分に能力を発揮して活躍できる可能性があるのです。
ADHDに関するよくある誤解と真実
ADHDについて正しく理解するために、特に経営者や職場の管理者が押さえておきたいポイントがあります。
大人のADHDは歴史的に認知が進んでいなかったため、いくつかの「誤解されやすいポイント」が存在します。
ここでは代表的な誤解とその真実を確認しましょう。
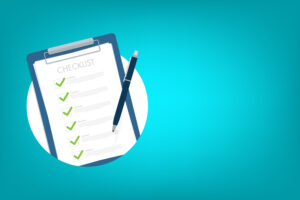
誤解①:「ADHDは子どもの病気で、大人には関係ない」
子どもの頃に症状が表れますが、前述の通り約半数は大人になってもADHDの特性が持続します。
近年ようやくDSM-5で成人期ADHDが公式に定義され、診断されるケースも増えてきました。
むしろ子どもの頃は見逃され、大人になって仕事で困って初めて診断に至る人も少なくありません。
大人にもADHDは存在するという前提で職場の人材を見る視点が重要です。
誤解②:「だらしないだけ・努力不足で、ADHDというのは甘えだ」
ADHDは医学的に裏付けられた脳機能の特性であり、本人の意思や性格だけではコントロールが難しい障がいです。
注意力や実行機能の障害により起こるミスや忘れ物を、「本人の怠慢だ」と決めつけるのは適切ではありません。
周囲から苦手なことをただ指摘されるだけでは当事者は深く傷つき、自信を失ってしまいます。
能力がないわけではなく、脳の特性によって能力を発揮しづらい状況だと理解し、必要なサポートを行うことが大切です。
誤解③:「ADHDなら誰でも多動で落ち着きがなく、問題行動ばかり起こす」
ADHDの症状の出方は人それぞれです。
不注意が目立ち多動はそれほどでもない人、衝動性だけ強い人、逆に集中力はあるが過集中になりすぎる人など様々です。
また大人の場合、目立つ多動よりも不注意傾向のほうが多いとされています。
一見穏やかでもミスや抜けが多いタイプのADHDもおり、一括りに「落ち着きがない人」とは限らない点に注意が必要です。
むしろそれぞれの特性に合った環境では、問題行動は起きにくくなります。
例えば静かな環境で一つの作業に集中できればミスが減る人もいます。適材適所と環境調整次第でいくらでも力を発揮できるのがADHDの人たちなのです。
誤解④:「本当にADHDなら好きなことにも集中できないはず。ゲームに熱中できるのはおかしい」
ADHDの人は興味の幅が独特で、好きなことには驚くほど集中する(過集中)一方で、興味が持てないことには注意を向けづらいという極端さがあります。
決して「何にも集中できない」というわけではありません。例えばクリエイティブな分野や研究開発など、自分の好きなテーマであればとことん追求し成果を出す人もいます。
したがって、好きなことに熱中している様子だけ捉えて「怠けでは?」と疑うのは誤りです。その強い集中力はむしろ適した仕事において大きな強みとなり得ます。
誤解⑤:「ADHDの人を雇用しても会社にメリットはないのでは?」
決してそのようなことはありません。
ADHDの人は発想力や行動力、旺盛なエネルギーといった優れた長所を持つことが多くあります。
思い立ったらすぐ行動に移せるフットワークの軽さ、感受性の豊かさや創造性は、ビジネスにもプラスに働く場面が少なくありません。
例えば次々と新しいアイデアを出せる企画力や、興味ある分野の知識を極める探究心などは、ある種の職務では大きな戦力となるでしょう。
企業側がADHDの強みに着目し活かすことで、本人にとっても会社にとってもメリットが生まれます。
実際の成功事例については後述しますが、適切な配慮のもと業務を任せればADHD人材が高い生産性や独創性を発揮した例も多く報告されています。
職場での人間関係:ADHDと上手にコミュニケーションするコツ
職場でADHDのある方と関わる際、何気ないやりとりが誤解やストレスのもとになることがあります。
ADHDの特性が原因で起こりやすいコミュニケーションのすれ違いを整理し、トラブルを防ぐための実践的な工夫を紹介。
また、当事者側が円滑な人間関係を築くためのポイントや、マネジメント層としての接し方・支援方法についても解説します。
相互理解を深めることで、誰もが働きやすい職場づくりを目指しましょう。
ADHD当事者が直面しやすい職場コミュニケーションの課題
ADHDの特性を持つ社員がいる職場では、何気ないやりとりの中にも誤解やすれ違いが生じることがあります。
本人・周囲それぞれの視点から、職場でよくあるコミュニケーション上の悩みを整理してみましょう。
【本人側の悩みの例】
「頼まれた仕事を自分なりにやってみたが、上司から『求めていたものと違う』と一方的に叱られてしまった。しかし何が悪かったのか自分ではよく分からない」
「なぜか特定の同僚に一方的に冷たくされているように感じ、その人とコミュニケーションを取るのがうまくいかなくなってしまった」
「指示があいまいで何を求められているのか分かりづらい。戸惑っているうちに時間が過ぎてしまい、また怒られるのではと不安になる」
「一度に色々な指示を受けると全てを覚えきれず、結局何をすればよいか分からなくなってパニックになる」
【周囲(上司・同僚)側の悩みの例】
「依頼した仕事に本人なりのアレンジが加わってしまい、頼んだ内容と違う成果物が出てきて戸惑った」
「ミスが起きたとき、原因や特性を考慮せず頭ごなしに叱責してしまったが、それ以降本人が萎縮してしまったようだ」
「こちらは伝えたつもりだったが、どうやら相手に伝わっていなかった。同じ前提を共有していると思い込んで話していたが、実は認識がずれていたようだ」
「丁寧に説明しようとするあまり、一度に情報を詰め込みすぎてしまい、結果的にほとんど相手に伝わっていなかった」
このように、「伝えたつもり」と「相手に伝わっていること」のギャップや、お互いの思い込みによるすれ違いは、職場のコミュニケーションでしばしば起こります。
ADHDの特性があるなしに関わらず起こり得ることですが、特性がある場合はその頻度や深刻さが増す傾向があります。
例えば、ADHDの人は指示の抜け漏れやあいまいさに気づきにくく誤解が生じたり、周囲は「普通これくらいできるだろう」という先入観で接してしまい、相互不信に陥るケースがあります。
結果として、本人は「また失敗して怒られた」と落ち込み、周囲は「何度言っても同じミスをする」といった不満を募らせ、コミュニケーションが悪循環に陥ってしまうのです。

対人トラブルを防ぐためのポイント
それでは、上記のような行き違いから深刻な対人トラブルに発展させないためには、どのような工夫ができるでしょうか。
以下に職場で実践できる具体的なポイントを示します。
指示・報告の仕方を工夫する
仕事の指示は口頭だけで済まさず、書面やメールでも明文化して伝えるようにします。ADHDのある人は頭の中で情報を整理するのが苦手なことが多いため、口頭指示のみだと漏れや勘違いが生じやすくなります。
ホワイトボードに箇条書きする、チャットツールで要点を送る、TODOリストを共有するといった形で、できるだけ具体的で明確な形にして伝達すると効果的。
また、「最終的に何を達成すれば良いか」を最初に示し、その後手順の詳細を教えるようにすると理解を助けられます。
コミュニケーションスタイルの好みは人それぞれなので、本人と対話しながら最も伝わりやすい方法を一緒に模索すると良いでしょう。
マルチタスクを避け順序立てて依頼する
「あれもこれも一度に対応してほしい」といった同時並行の依頼は避けます。ADHDの人は一度に複数のことを処理するのが苦手な傾向があり、結果的にどれも中途半端になってミスが増える恐れがあります。
一つひとつのタスクが完了したら次のタスク、というように優先順位を明確にして順番に依頼する方がうまくいきます。
「まずはAの資料作成を終えてから、その次にBのデータ整理をお願いします」のように段階的に伝えるようにしましょう。
曖昧な表現を避けフィードバックを丁寧に
「適当にやっておいて」「いつも通りに」など曖昧な指示は誤解のもとです。
可能な限り具体的な期待値や基準を伝えます。また成果物が期待と違った場合も、頭ごなしに否定するのではなくどこがズレていたのか具体的にフィードバックしましょう。
「ここは○○してほしかった」とポイントを示せば本人も次回から修正できます。
感情的に叱責すると委縮してしまい逆効果なので、冷静に事実ベースで伝えることが大切です。
本人の特性をチームで共有する
可能であれば、当事者が自分の特性や得意不得意について職場の人に事前に説明しておくと相互理解が進みます。
とはいえ、いきなり自分のことをうまく説明するのは難しいもの。
そこで、自分の取り扱い説明書、いわゆる「自分のトリセツ」を作成してみる方法があります。
自分の性格や苦手なこと・得意なこと、配慮してほしいポイントなどを書き出し、上司や同僚に共有するのです。
書いたものを渡すだけでなく、顔を合わせて補足しながら伝えることで細かいニュアンスも理解してもらいやすくなります。
こうしたオープンな情報共有によって、周囲も配慮すべき点が把握でき、トラブルの予防につながります。
もちろん内容は本人の意向を尊重し、共有範囲も限定して構いません。
重要なのはお互いの特性やクセを認め合いながら働くという姿勢を職場全体で持つことです。
ミスをフォローし合える風土づくり
人間ですから誰しもミスはあります。
ADHDのある人はミスの質や頻度に偏りがあるかもしれませんが、チームで補えば大事に至らないことがほとんど。
「お互い様」の意識で、困ったときは助け合う風土を作りましょう。
例えば、「忘れていそうだったから声をかけました」「確認リストを一緒に作りましょう」といった声がけがあるだけで、本人も安心感を持てます。
これは多様な人が働く組織全体にとってプラスであり、結果的に生産性向上にもつながります。
ADHD当事者が円滑な人間関係を築くための工夫
次に、当事者であるADHDの社員側が心がけると良いポイントについても触れておきます。企業として社員教育やサポートの中で促していくと、より良い相互コミュニケーションにつながるでしょう。
自己理解を深め対処法を身につける
自身のADHD特性を正しく理解し、仕事で困りがちな状況を把握しておくことは大切です。例えば「自分は長時間の会議だと集中力が切れやすい」「口頭指示だけだと漏れが起きやすい」等を自覚できれば、メモを取る、適宜確認質問をする、といった自己防衛策が取れます。
企業側も研修やカウンセリング機会を提供し、本人の気付きとセルフマネジメントを支援すると良いでしょう。
専門家の指導のもと認知行動療法などを活用し、自分の行動パターンを客観視して改善するトレーニングも効果があります。
周囲へのオープンな情報提供
前述の「自分のトリセツ」を活用するなどして、信頼できる上司や同僚に自分の特性を伝えておくことは、当事者にとっても助けになります。
言いにくいこともあるかもしれませんが、「実は自分は整理整頓が苦手なので、何か散らかっていたら教えてください」のようにお願いしておけば、周囲も協力しやすくなります。
無理のない範囲で構いませんので、自分の苦手な部分やサポートしてほしい点を発信する勇気も持てると理想的です。
コミュニケーションの基本スキルを見直す
ADHDの有無にかかわらず、報連相(報告・連絡・相談)は社会人の基本です。
特性によりこれが苦手な場合こそ、意識的に練習してみましょう。
例えば、「要点を一枚の紙にまとめてから報告する」「話す前に深呼吸して頭の中を整理する」など、自分なりの工夫が役立ちます。
また、仕事で困ったときやミスをしたときは早めに周囲に相談・報告するクセをつけましょう。
言い出しづらく先延ばしにすると状況が悪化し、人間関係の悪化にもつながります。
勇気を出して早めに打ち明ければ、周囲もフォローしやすく大事になりにくいものです。
感情コントロールとストレスケア
衝動的にカッとなって怒りをぶつけてしまうと、人間関係の修復には時間がかかります。アンガーマネジメント(怒りのコントロール法)を学んだり、ストレス発散法を日頃から実践しておくことも有用です。
例えば、ゆっくり10秒数えてから発言する習慣をつける、業後に運動をしてストレスをためない、といった工夫です。
会社としても、産業医やカウンセラーと連携してメンタルヘルス面の支援体制を整えておくと良いでしょう。
周囲の理解とサポートの重要性
ADHDのある社員本人の努力だけでなく、周囲の理解と支援があってこそ、職場の人間関係は円滑になります。
上司や同僚がADHDという特性について正しく理解し、必要な配慮を示すことで、当事者は能力を発揮しやすくなり、周囲もストレスが減るという効果があります。
周囲の人にはぜひ、「苦手なことは本人の能力不足ではなく特性によるものだ」という視点を持っていただきたいと思います。
ただ単に苦手な点を指摘・非難するのではなく、「どうすればうまくいくか一緒に考えよう」という建設的な姿勢で接することが大切。
ミスがあった場合、「次からはどう防ぐ?」と問いかけ一緒に対策を考える、といったアプローチです。
これは当事者にとって「自分は見捨てられていない、一緒に改善できる」とポジティブな安心感を与えます。
逆に頭ごなしに叱責されたり人格否定されると、「どうせ自分なんて…」と意欲を失い、関係も悪化してしまいます。 また、得意なことに目を向けて称賛することも忘れないでください。
ADHDの人にも必ず得意分野や長所があります。周囲がそれを発見したら積極的に言葉に出して伝えましょう。
「あなたの発想はクリエイティブで助かる」「集中力が必要な場面では力になるね」といったフィードバックは、当事者に「自分は必要とされている」という前向きな気持ちをもたらし、コミュニケーションをより良好にします。
苦手の対応と同時に得意を活かす――この両面に目を向けることが、チーム全体の活力にもつながるのです。
総じて、当事者と周囲がお互いに得意・不得意を認め合い補い合う姿勢が、人間関係円滑化の鍵と言えます。
これはADHDに限らずあらゆる人間関係に通じる基本ですが、特にADHDの場合はその凹凸が大きいため意識して取り組む意義が大きいでしょう。
マネジメント層ができる支援と接し方のコツ
中小企業の経営者や管理職の立場からは、ADHDのある部下・社員に対しどのように接すると良いでしょうか。
前述のポイントと重なる部分もありますが、マネジメント視点での対応策を整理します。
業務指示・コミュニケーション方法の調整
マネージャーは部下ごとに最適な指示の出し方を工夫する責任があります。
ADHD傾向の部下には、先述した明確で視覚的な指示を行う、優先順位を示して一つずつ依頼するなどの方法を実践しましょう。
会議の進め方も、長時間だらだらと続けるより、要点を区切り休憩を挟む方が集中を保てます。
上司がそうした働きかけを意識するだけでも、本人のパフォーマンスは大きく向上します。
担当業務や配置の見直し
業務上で何度もつまずく場合、その人の適性に合っていない可能性を検討しましょう。ADHDの人は能力にムラがあることが多く、不得意な業務に固執しても成果が上がりにくい場合があります。
思い切って担当替えをしたり、役割を再調整することで本人の持ち味が活きるケースもあります。
例えば、細かい事務処理でミスが多い人には、代わりに企画アイデア出しやフィールドワーク的な仕事を任せたら生き生きと活躍し始めた、といった例もあります。
上司は部下の適材適所を常に考え、必要なら大胆に業務内容を調整することを躊躇しないでください。
幅広く色々な仕事を経験させる中で意外な才能が見つかることもあります。
接し方のスタイルを柔軟にする
部下との人間関係がうまくいっていないと感じたら、上司側の接し方を変えてみるのも一つの手です。
管理職にはそれぞれスタイルがありますが、ADHDの部下には特に「頻繁に声かけして進捗確認する」「結果より過程も評価する」などの工夫が有効な場合があります。
例えば進捗管理が苦手な部下には、こまめなチェックインやリマインドを行うことで締め切り遅れを防げますし、ミスが多い部下でも努力している過程を認めてあげればモチベーション維持につながります。
管理職自身も部下に合わせたマネジメントスタイルの柔軟性が求められるのです。
専門家や支援機関との連携
部下のADHD傾向が強く業務に支障が出ている場合、社外の専門家に相談することも検討しましょう。
産業医やカウンセラーに助言を仰いだり、必要に応じて受診を勧めることも選択肢です。
ただし、すべてのケースで無闇に「病院に行け」と促すのは逆効果な場合もあります。
本人が強いストレスで苦しんでいる様子なら医療的支援が必要ですが、そうでない場合は職場内の対応改善だけで状況が好転することも多いです。
むしろ診断の有無に関わらず現場でできる配慮を上司が率先して行うことが先決です。
それでも難しいときに専門家の力を借りましょう。また、公的な「ジョブコーチ」制度なども利用できますので(後述)、必要に応じて外部資源を活用する柔軟さも経営者には求められます。
障がい者雇用でADHD人材を活かすために企業ができること
ADHDのある人材を雇用し、職場で活躍してもらうには、企業側の理解と具体的な対応が欠かせません。
障がい者雇用の基本的な制度から、採用・配属時の配慮、職場環境の工夫、活用できる支援策、そして実際の成功事例まで幅広く紹介します。
ADHD人材の強みを引き出すことで、企業にもたらされるメリットや職場全体の変化についても解説します。

障がい者雇用の制度と企業の責任(基本の理解)
日本には、障がいのある人の雇用機会を促進するため「障害者雇用促進法」に基づく法定雇用率制度があります。
一定規模以上の企業(従業員43.5人超)は、全従業員のうち約2.3%以上(民間企業、2023年現在)を障がい者とすることが義務付けられており、未達の場合は納付金が課せられます。
今後この法定雇用率は段階的に引き上げが予定されており、3年後には2.7%に上昇することが発表されています。
つまり、中小企業であっても将来的にはより多くの障がい者雇用を検討する必要が出てくる可能性が高いのです。
では、ADHDのある人はこの「障がい者雇用」の枠組みに含まれるのでしょうか。
ADHDは発達障がいの一つであり、日本では精神障害者保健福祉手帳(通称:障害者手帳)を取得することで法定雇用率の対象となるケースが多いです。
2018年以降、発達障がいや精神障がい者も法定雇用率に算入されるようになり、企業で働くADHD当事者も増加傾向にあります。
したがって、企業がADHD人材を採用する際は、その人が障害者手帳を所持している場合雇用率カウントの対象となり、各種助成や支援策の利用も可能です(手帳を持たない場合でも活用できる制度がありますので後述します)。
また2016年から施行された「障害者差別解消法」により、合理的配慮の提供義務が民間企業にも課せられています。
これは、障がいのある従業員が能力を発揮できるよう、業務上支障のない範囲で職場環境や勤務条件の調整(配慮)を行う義務です。
ADHDの社員に対して、業務上の工夫(指示方法の変更や環境整備など)を行うことも合理的配慮の一環です。
もちろん企業規模や業種によってできる範囲は異なりますが、「できる配慮はしっかり行い、不当な扱いをしない」ことが法律で求められている点を認識しましょう。
差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供は、もはや企業にとって義務であり、障がい者雇用を検討する際の大前提となっています。
要するに、中小企業経営者にとっても、ADHDを含む障がい者雇用は避けて通れないテーマになりつつあります。
ただ義務だから雇い入れるのではなく、戦力として活躍してもらうには何ができるかを前向きに考えることが重要です。
採用・配属時に企業が配慮すべきポイント
1. 採用選考時のポイント
ADHDのある応募者を採用面接する際は、まずその人の強みと適性に注目することが大切です。
障がいの内容ばかりを詳しく聞きすぎるのではなく、どんな分野で力を発揮できるか、どんな配慮があれば能力を最大限出せるかに焦点を当てます。
必要に応じて履歴書や職務経歴書では汲み取りづらい部分を質問し、能力を正当に評価しましょう。
また、緊張やコミュニケーションの苦手さで面接では実力が出せない場合もあります。
そのようなときは、職場見学や実習の機会を設けることも有効です。
実際に職場で1日~数日働いてもらい、お互いに理解を深めるのです。ある介護業界の企業では、応募者に会社見学と1週間の実習を経てから正式に採用したケースがあります。
この間にパソコンスキルの高さや真面目にやり遂げる姿勢が確認でき、「戦力になる」と判断して採用の決め手になったとのことです。
このように、一定期間のトライアル雇用を活用する方法もあります。ハローワークには「障がい者トライアル雇用制度」があり、原則3か月の試行雇用で適性を見極めてから本採用に移行することも可能です(この制度を利用すると助成金も受けられます)。
中小企業にとってはいきなり本採用するよりリスクを抑えつつ相互理解できるメリットがあります。
2. 配属・担当業務決定時のポイント
採用後は、その人の特性にマッチしたポジション・業務を考えることが重要です。
先に述べたように、ADHDの人には突出した得意分野がある一方で苦手分野も明確です。適材適所の配置を心がけましょう。
例えば、細かい事務ミスが心配ならダブルチェック体制を敷くか、思い切ってクリエイティブな企画部署に回してアイデア発想力を活かしてもらう、といった柔軟な配属も一案です。
実際に、あるメーカーでは人事部門に発達障がいの方を受け入れたところ、個人作業中心だった部署において他社員が互いの業務状況を気にかけ協力する契機となり、結果的に部内の風通しが良くなったという報告があります。
当初は受け入れに不安を感じていた社員もいましたが、実習を経て「後回しにしていた仕事が片付いて助かった」「発達障がいへの見方が変わり理解が深まった」といった前向きな声が上がったそうです。
この例からも、業務内容の工夫と周囲の協力次第でADHD人材は十分に力を発揮し、組織にも良い影響をもたらすことが分かります。
3. 面談と情報共有
入社前後には、人事担当や直属の上司が本人としっかり面談を行い、必要な配慮事項を確認・共有しましょう。
例えば「どんな環境だと働きやすいか」「どんなサポートがあると安心か」といった点です。本人がまだ自分の特性を把握しきれていない場合もありますので、徐々にコミュニケーションを重ねる中で掘り下げていくと良いでしょう。
ここで聞き取った内容は、現場の上司やチームメンバーにも(本人の同意を得て)共有し、組織として受け入れ体制を整えます。
「特別扱い」ではなく「必要な配慮」として皆が理解することが大切です。
職場環境の整備と具体的な合理的配慮の例
ADHDの社員が能力を発揮するには、働く環境づくりも重要です。
企業側でできる具体的な職場環境の工夫(合理的配慮)をいくつか挙げます。
業務遂行をサポートするツールの活用
例えばタスク管理やスケジュール管理を支援するツールを導入し、誰でも見える形で進捗を共有します。
チェックリストやカレンダー共有ソフト、リマinderアプリなどを活用すると、ADHDの人が忘れやすい案件や締切もフォローできます。
また、集中力が続かない場合に備えてポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩のサイクル)を導入するなど、組織全体で生産性を上げる工夫として取り入れてみるのも良いでしょう。
作業環境の騒音・刺激をコントロール
注意散漫になりやすい人には、オフィスの席をできるだけ静かな場所に配置したり、パーティションで区切るなど配慮します。
ヘッドフォンで環境音を遮断できるようにするのも一案です。
逆に刺激が少なすぎて眠気が出る場合は、適度に人の目がある場所に席替えするなど、その人に合った環境を一緒に模索します。
フリーアドレス制で自分の集中しやすい場所を選べるようにするのも有効でしょう。
休憩やタイムマネジメントのサポート
ADHDの方は集中し始めると休憩を忘れて没頭してしまうことがあります。
適切にリフレッシュしないと後で疲労やストレスが噴出する恐れがあるため、周囲が「〇時ですよ、一旦休憩しませんか」と声をかけるなど促しましょう。
就業時間の区切りも曖昧になりがちなので、終業時刻になったら切り上げるよう声掛けする配慮も場合によっては必要です。
労務管理の観点からも大切なポイントです。
ジョブコーチ等専門支援の導入
必要に応じて、ジョブコーチ(職場適応援助者)の支援を受けることも検討しましょう。ジョブコーチは障がい者が職場に適応できるよう企業内外でサポートしてくれる専門家で、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「職場適応援助者助成金」を活用して派遣を受けたり、企業内で配置することもできます。
ジョブコーチは本人への業務指導だけでなく、周囲の社員への助言や職場内の調整も行ってくれます。
特に中小企業では障がい者雇用のノウハウが蓄積しにくいため、外部リソースを活用して専門知識を取り入れることは有効な戦略です。
勤務制度の柔軟化
ADHD特性によっては、朝の通勤ラッシュで消耗してしまう人や、通院・服薬の関係で勤務時間に配慮が必要な人もいます。
テレワークや時差出勤、フレックスタイムなどを導入できる場合は検討しましょう。コアタイムだけ出社してもらい、あとの時間は在宅勤務にする、といったハイブリッドな働き方も選択肢です。
大事なのは成果で評価し、働き方は柔軟にする姿勢です。
中小企業でも可能な範囲で制度を調整すれば、ADHDに限らず多様な社員が働きやすい職場となり、結果的に定着率向上にも寄与します。
以上は一例ですが、「その人が働きやすい工夫」を対話しながら実施すること自体が合理的配慮となります。
なお、こうした取り組みはADHDの社員だけ特別に行うというより、職場全体の業務改善策として進めると自然です。
例えば「業務マニュアルを整備する」「進捗見える化ツールを導入する」等は、全社員の生産性向上策にもなります。
ADHD当事者も遠慮なく活用でき、他の社員からも不公平感が出にくいでしょう。
活用できる公的制度・支援サービス
障がい者雇用を進める企業向けに、行政や支援機関が様々なサービスを提供しています。ADHD人材の採用・定着に役立つ主な制度を紹介します。
ハローワークの「発達障害者雇用支援チーム」
ハローワークには「精神・発達障害者雇用サポーター」が配置されており、発達障がいや精神障がいのある求職者の就職支援や、事業主からの雇用相談に応じています。
求人のマッチングから職場定着まで一貫してサポートが受けられる「チーム支援」体制も整っているので、障がい者雇用未経験の中小企業でも安心です。まずは最寄りのハローワークに相談するとよいでしょう。
障害者トライアル雇用助成金
前述した試行雇用(トライアル雇用)を実施した場合、一定の要件のもとで国から助成金が支給されます。
発達障がい者の場合、中小企業で1人あたり月額4万円・最長3か月の奨励金を受け取ることができます(※金額は年度により変更あり。最新情報は厚労省資料参照)。
この助成金は、試行雇用終了後に本採用に至らなくても支給されるため、企業側のチャレンジを後押ししてくれます。
発達障害者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介で発達障がい者を継続雇用した事業主には、「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者コース)」を受給できる場合があります。
中小企業では一人当たり最大135万円(大企業50万円)の支給が受けられます。
こちらは障害者手帳を持たない発達障がいの方を雇用した場合にも対象となるコースが用意されています。
助成金は予算や年度で変更もありますので、最新の厚生労働省情報を確認してください。
地域障害者職業センターの活用
各都道府県にある地域障害者職業センター(独立行政法人JEEDが運営)では、職業準備訓練や職場適応援助(ジョブコーチによる支援)など専門的なリハビリテーションサービスを提供しています。
発達障がい者に特化した支援プログラムも開発・実施されており、企業からの相談にも応じています。
「どのように仕事を教えればいいか」「職場で困ったときにどう支援すればいいか」といった具体的な悩みに対し、専門スタッフがアドバイスしてくれます。
ジョブコーチの派遣もセンター経由で可能です。
就労移行支援事業所との連携
発達障がいのある方の中には、一般企業へ就職する前に「就労移行支援事業所」で職業訓練を受けている人も多くいます。
そうした事業所ではビジネスマナーやPCスキル習得、実習などを通じて働く準備を支援しています。
事業所から企業へ職場実習の提案が来ることもありますし、企業側から「どんな人材がいるか紹介してほしい」と問い合わせることもできます。
就労移行支援を経ている人材は一定のトレーニングを積んでいるため、職場適応がスムーズになる利点があります。
発達障がい人材の活躍事例に学ぶ企業のメリット
最後に、ADHDをはじめ発達障がいのある社員を受け入れた企業の成功事例と、企業にもたらされるメリットについて触れておきます。
事例:製造業A社のケース
ある製造業の中堅企業A社では、人事部門で発達障がい(ADHDとASDの特性)のある社員Aさんを受け入れました。
当初、同じ部署の社員には「どんな人が来るのだろう」「職場になじめるだろうか」と不安もあったそうです。
そこでA社は入社前に職場見学を実施し、入社後も周囲がサポートしやすいよう特性について事前に共有しました。
Aさん自身も非常に前向きで真面目に仕事へ取り組み、違和感なく社内に溶け込んだといいます。
業務を進める中で、上司や同僚は「Aさんに頼むときは今どのくらいタスクを抱えているか配慮しよう。皆が自分のペースで次々仕事を振ったらAさんが困ってしまう」ということに気づきました。
結果として、部内の誰もが他の人の仕事状況を意識するようになり、チームで助け合う意識が芽生えたのです。
実習期間終了後には「後回しにしていた仕事が片付いて助かった」「発達障がいに対する考えが変わり理解が深まった」という声も上がり、Aさんを迎え入れてから多様性を認め合う風通しの良い職場になったと感じる社員が増えたそうです。
このケースでは、Aさん自身の働きぶりもさることながら、受け入れた組織全体にプラスの変化が生まれた点が注目すべきポイントです。
企業にとってのメリット
上記のような事例から分かるように、ADHDを含む発達障がい人材の雇用は単に義務を果たすだけでなく、企業に様々なメリットをもたらし得ます。

業務効率の改善
ADHD社員の特性に合わせて導入した仕組み(見える化やマニュアル化)は、他の社員のミス防止や業務標準化にも役立つケースが多々あります。
「誰にでも分かる伝え方」を追求した結果、組織全体のコミュニケーションが向上した、という例もあるでしょう。
特性への配慮として始めたことが職場全体の生産性向上策になることも少なくありません。
組織の多様性と創造性向上
ADHDの人が持つ独特の発想力や行動力は、従来になかったアイデアや視点をもたらす可能性があります。
社内に多様な考え方・強みを持つ人材がいることでブレインストーミングが活発になり、新規事業のヒントが生まれることも期待できます。
実際に「興味のあることへの集中力」を活かして製品開発分野で成果を上げている社員がいる会社もあります。
多様性(ダイバーシティ)を受け入れることは創造性やイノベーションの源泉ともなるのです。
職場風土の向上
発達障がいのある社員が活躍できる職場は、裏を返せば誰にとっても働きやすい職場です。社員同士が助け合い、コミュニケーションのズレに気を配る風土は、健常者同士のチームワークにも良い影響を与えます。
お互いの得意不得意をフォローし合う文化が根付けば、社員のエンゲージメント(愛社精神)も高まり離職率低下にもつながるでしょう。
前述のA社の例でも、多様性を受け入れる姿勢が強まり風通しが良くなったとのことです。障がい者も健常者も区別なく活躍できる職場づくりは、結果的に組織全体の士気を高めることにつながります。
人材確保と企業価値の向上
昨今、人手不足が深刻化する中で、障がい者雇用は新たな人材層の開拓でもあります。特に精神・発達障がい者の求職者数は増加傾向にあり、企業間の採用競争も激しくなると予測されています。
いち早く受け入れ態勢を整え多様な人材を活用できる企業は、将来的な人材確保において有利になるでしょう。
さらに、障がい者雇用に積極的に取り組む姿勢は企業の社会的評価(CSR)向上にも寄与します。
「誰もが活躍できる職場」を掲げ実践することで、取引先や顧客からの信頼が増し、優秀な人材も集まりやすくなるという好循環が期待できます。
まとめ:大人のADHDの特徴と人間関係のコツ
中小企業の経営者層の皆さまにとって、障がい者雇用は未知のチャレンジかもしれません。しかし、正しい知識と適切な配慮があれば、ADHDを持つ社員もその人ならではの力を発揮し、会社の発展に貢献してくれる貴重な戦力となり得ます。
実際、多くの企業でADHD・発達障がいのある方が安定就労を実現し、職場の推進力となっている事例があります。
企業文化として多様性を受け入れ、社員一人ひとりの個性を活かすことは、これからの時代に求められる経営戦略でもあります。
ADHDへの理解を深め、適切なコミュニケーションと環境整備を行うことで、誰もが働きやすい職場づくりを進めていきましょう。
株式会社アルファ・ネットコンサルティングでは、アクセルというサービスを提供しています。
「法定雇用率を満たせない」
「採用後に長く働いてもらえるかわからない」…という企業様向けに、
障がい者雇用枠で新規顧客開拓のスぺシャリストを採用し、
ADHDの特性を活かし、貴社の営業力を強化するためのサービスを提供しています。
サービス資料ダウンロードはこちらよりご確認ください。




